ディベート(討論)にはメリットがありますが、デメリットもあります。二者択一で考え、合意形成ではなく勝つことが目的になります。理解を深めるよりも、プレゼン力、雄弁さなど、スキルや印象に結果が左右されるライブパフォーマンスになります。必ずしも正しい方が勝つわけでもありません。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
世の中には白黒付けることが難しい問題がたくさんあります。
観光地でのオーバーツーリズム対策として、観光客の人数を制限すれば地域のルールは守られますが、観光収入が減って地域経済に悪影響を与えます。
最低賃金を引き上げれば、労働者の収入は改善しますが、人件費が上がることで、物の値段がさらに上がるかもしれません。
大型音楽フェスの開催規制をすれば、騒音やごみ問題が減り、周辺住民の生活環境は守られますが、フェスによる経済効果が失われ、音楽ファンはがっかりしてしまうかもしれません。
ヨーロッパの多くの国々やシンガポール、ジャカルタなどのように、都市内への車の乗り入れを制限すれば、渋滞緩和や大気汚染は軽減されますが、利便性は失われてしまいます。
このように、賛成か反対か簡単に判断することができない問題が世の中にはたくさんあるのです。
~ ~ ~ ~ ~
ディベート(討論) とは?
ディベート(討論) とは、あるテーマについて、賛成側と反対側に分かれて、論理的な根拠や証拠をもとに議論を行い、どちらの立場がより説得力があるかを競うものです。
例えば「小学生にスマートフォンを持たせるべきか」というテーマに対して、賛成、反対、それぞれの立場に分かれて、根拠やデータをもとに主張し合います。
賛成側は「スマホは緊急時の連絡手段になる」とか「持っていないと仲間外れになる」と主張するかもしれません。
反対側は「勉強の妨げになる」とか「有害なサイトに誘導されたり、闇バイトなどの犯罪に巻き込まれる」と主張するかもしれません。
次に、相手側に対して論理的に反論したり、自分の主張を補強したりします。
賛成側は反対側に「うまく使えば、スマホは勉強の助けになる」と反論するかもしれません。
反対側は賛成側に「みんなが持つことをやめれば仲間外れにならない」と主張するかもしれません。
そして、最後にどちらの主張がより説得力があるか、聴衆や審査員が判断します。
ディベートによって、私たちは、論理的思考、情報収集力、分析力、表現力、コミュニケーション能力、交渉力を磨くことができます。証拠を集めたり、自分の考えをまとめたり、論理的に組み立てて説明する力を養ったり、批判的に考える力を高めることができます。また、他人と主張を交わすことで、多様な視点が明らかになったり、前提に間違いがないか検証することもできます。
それらの点ではディベートは有効ですし、そのようなスキルを身につけるという目的で行われる限りはディベートは有益です。
しかし、テーマや論題そのものに白黒をつけることを目的とすると、有益でないどころか、有害となる可能性もあります。
実は、ディベートには、メリットとデメリットがあります。
今回はディベートのデメリットにフォーカスして考えていきます。
~ ~ ~ ~ ~
ディベートのデメリット
では、ディベートのデメリットを列挙していきましょう。
1.二者択一を求められる
ディベートは、本質的に対立的です。
あるテーマに対して「賛成」か「反対」か、相反する2つの立場のどちらかを取ることが迫られます。
批判的思考や表現力を養うことはできますが、同時に対立や二極化を引き起こすことがあります。参加者はお互いの共通点を探るのではなく、自分の立場に固執してしまうことがあります。
どちらか一方を選ばなければならないとき、私たちは反対意見の正当性や、議論の背景にあるニュアンスを無視してしまいがちです。理解を深めたり、妥協点を探ったり、創造的に考えることは阻害され、議論は探究的というより敵対的なものになりがちです。
政治、倫理、テクノロジー、環境などの現代社会が抱える問題は、複雑な要因や様々な立場が絡み合っていて、その解決策は白黒はっきりした単純なものにはなりません。しかし、そのような複雑な議論でさえも、両極端のどちらかで考えてしまうのです。
- 中絶に賛成ですか?反対ですか?
- 銃規制に賛成ですか?反対ですか?
これらはアメリカで長く繰り返される政治的かつ社会を二分するテーマです。
何が何でも中絶に反対という保守派の人たちがいます。しかし、状況によっては中絶を認める人たちもいます。銃規制に関しても、単純に規制に賛成か反対かではなく、本来はどのような規制にするかがより重要でしょう。
「賛成」か「反対」では、人が置かれた立場や状況の違いから生じる微妙なニュアンスをくみ取ることはできません。
現実は、はるかに複雑です。多くの場合、答えはそのどちらかではなく、その間のどこかにあるのです。
2.議論に勝つことが目的になっている
ディベートは「どちらが優れているか」を競うものです。
相手のことをもっと理解するよりも「勝つ」ことが優先されます。
相手の主張に「確かにそうですね」と同意したり、「もっと詳しく聞かせてもらえますか」とお願いするのではなく、反論のネタ探しや、相手のロジックを覆すことに必死になります。
始める前から、対立的な姿勢を取ることもあり、本来の問題解決は後回しになります。
勝つために極端な意見や偏った主張を展開することもあり、バランスの取れた議論は難しくなります。ひどい場合は、個人攻撃につながることもあります。
しかし、どちらが正しく、どちらが間違っているかにフォーカスすると、視野が狭まります。トンネル効果によって、その他の選択肢が見えにくくなり、建設的な議論は妨げられます。
ヴァージニア軍事大学のエミリー・リリー教授(Emily Lilly)による2012年の研究では、討論に参加する生徒に特定の立場を割り当てると、生徒が自分の考えに基づいて結論を導き出す能力が著しく阻害されることが判明しました。(1)
討論を第三者の立場で観るだけでも、どちらかの立場を知らずに支持するようになり、その証拠だけを恣意的に選び、対立する証拠は無視するようになることさえあります。これには確証バイアス(confirmation bias)が影響しています。
つまり、討論は無益なだけでなく、有害になることもあるのです。
3.真実よりもその場の説得力が重要になる
ディベートでは「相手よりいかに説得力のある主張をするか」が決め手になります。意見そのものよりも、説得力、組み立て方、プレゼンの仕方、雄弁さ、自信があるように見せることが重要です。
つまり、スキルの差によって結果が左右されます。必ずしも正しい方が勝つわけではありません。
また、ディベートには、時間の制限があることが多いので、複雑なテーマをじっくり掘り下げている余裕はありません。
正確さや深い洞察よりもその場での説得力が優先されます。多方面からの物事の理解や熟慮された分析よりも、単純化された分かりやすいスローガン的な主張や、それらしく聞こえる印象の良い発言が評価されることもあるのです。
さらには、ディベートはライブパフォーマンスであるため、内容よりもその人の見た目や人気やイメージに影響されます。
ディベートスキルの高い人は、膨大な量の知識を頭の中に蓄え、他者と対決しながら、それらを素早く言葉にまとめ上げることができます。誤った情報さえそれらしく主張したり、相手を説得するために事実を操作できる人もいます。
一方で、物事を深く掘り下げられる鋭い洞察を持っている人でも、印象がよくないとか、話すのが遅いというだけで負けてしまうこともあるのです。
4.感情や価値観の対立を生みやすい
ディベートは、個人的な攻撃や感情的な言い争いにつながることがあります。
相手を尊重せず、感情が論理を凌駕し、場を支配してしまうこともあります。
司会者や、ファシリテーターも、両者の共通点を見出して歩み寄りを探るのではなく、参加者にプレッシャーを与えたり、問い詰めるスタイルで、合意よりも対立を扇動することがあります。
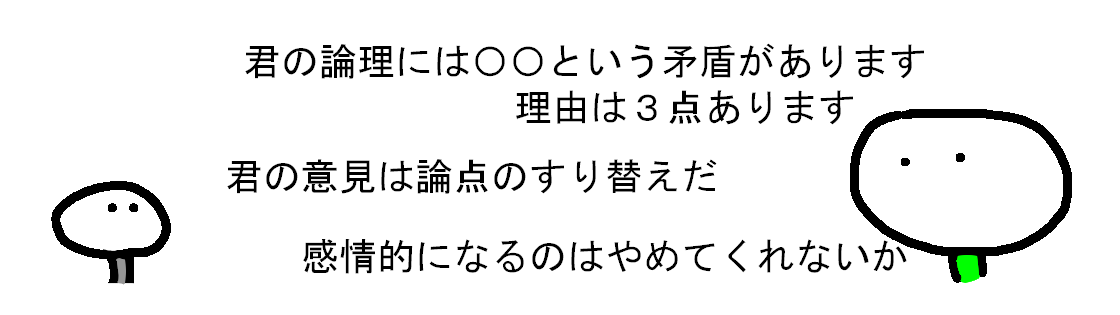
~ ~ ~ ~ ~
勝つことではなく、理解することを目指す議論
良い議論をするためには、対話や協調の姿勢を持ち、建設的な意見交換を目指すことが重要です。
私たちが行うべきなのは、相手に勝つことではなく、相手を理解することを目指す議論です。相手を打ち負かすことではなく、非敵対的議論または協働的対話と呼べるような「探究型のディスカッション(inquiry-based discussion)」です。
なぜなら、すべては理解すること、そして理解したことを認めることから始まるからです。
ゴールは相手に勝つことではなく、相手を理解することである。
~ 高宮あきと
The goal is not to win, but to understand.
~ Akito Takamiya
集団理解を深め、新たな洞察を生むのです。そうすることで、当初は誰も想像していなかった新たな視点にたどり着くこともあります。
そのような議論の進め方を以下に記します。
1.目的を定める。相手に勝つことではなくお互いを理解する
「一方が正しく、一方が間違っている」というディベートの罠にはまるのを避けましょう。
そのために、議論の目的を相互理解を深めることにするべきです。はじめに、そのことを参加者全員の共通認識にしましょう。
相互理解とは、相手に自分の意見を受け入れるように説得することではなく、なぜ違いがあるのかを知ることです。違いの背景を知り、それを受け入れることです。
参加者の誰かが防御するような発言をしていたら、勝ち負けの議論に陥っていると思ってください。相互理解の結果、勝者や敗者が生まれることはありません。
ファシリテーターがいる場合は、「私たちの目標は、どちらが優れているかを決めることではなく、互いに学び合うことです」と最初に目的を明確に示すのです。
公共政策学教授のマイケル・A・ネブロ(Michael A. Neblo)らの論文は、参加者が勝利ではなく理解に焦点を当てると、意思決定はより情報に基づいた公平なものになることを示しています。(2)
ネブロらは、他者の意見に耳を傾けながら自らの立場を修正する態度を持って議論することを目指す熟議民主主義(Deliberative democracy)を支持しています。
2.反論ではなく、質問をする
学校では、手を挙げて自分の意見を積極的に発言できる生徒が評価されます。
私たちの社会では、聞くことよりも話すことの方が高く評価されるからです。
話す = 積極的、エネルギーに満ちている、自分が主張できる、ポジティブ
聞く = 消極的、自分の意思がない、流されている、ネガティブ
ずっと静かに聞いていて「よく静かに聞いていましたね」と先生から褒められることはありません。
相手の話を聞く技術は、学校でも家庭でも職場でも教えられません。
また、人気、声の大きさ、見た目などの議論とは関係のない要因が、評価に深く影響します。自信があり口が立つ学生は討論で優位に立つ傾向があり、物静かだが他人の意見をよく聞く生徒は討論で不利になります。
ディベートのスキルが高い人は、様々な点で社会的に評価されやすいのです。
しかし、共に理解を深めるためには、説得するのではなく、質問することが求められます。相手の話をよく聞いてそれを知ることが求められます。効果的な質問は、「なぜそんなに間違っているのですか?」ではなく「なぜそう考えたのですか?」です。
私たちは人の話を聞くのが不得意です。つまり、不得意なことをしなければなりません。それを克服するためには常に意識していなければなりません。参加者に他の視点を要約してもらうルールとすることも効果的です。
3.ルールを定める
目的と共に、対話のガイドラインやルール、プラットフォームを定めます。議論そもそもの組み立て方に問題がある場合、第一ボタンを掛け違えたまま他のボタンをかけ続けてしまうように、最後まで掛け違えたまま進み、修正できません。
例えば次のようなルールを設定します。
- 初めに、参加者全員が順番に自分の考えをみんなと共有する。また、その前提を述べる
- 自信がなくても不確実でも、参加者が安心して共有できる心理的安全性を確保する
- すぐに反論しようとするのではなく、一呼吸おいて相手の話をよく聞き、相手を理解するための質問をする
- 攻撃して相手を防御させるのではなく、理由を尋ねる
- 相手の意図について勝手な憶測をしない
- 相手の性格や特性ではなく、推論と証拠に焦点を当てる
- 可能な限り、複数の立場からの知見、様々な角度からの見方を組み合わせる
以前、そのようなガイドラインの例として、アメリカのセント・ジョンズ・カレッジ(St John’s College)が採用している討議の作法を紹介しました。ここではその詳細は割愛しますが、ご興味があれば、こちらのリンクから、そのガイドラインをご参照ください。
4.グループを「賛成派」「反対派」の2つに分けない
「どちらが正しいか」という議論になるのを避けるためには、そもそも「どちら」という立場を作らないこと、つまり、グループを2つに分けないことです。対立する関係を作ることで、勝つように動機づけられた推論や、防御的な態度を引き起こすのです。
また、多数派の主張に対して、意図的に反論をするような役割を与えられる人を「悪魔の代弁者(devil’s advocate)」と言いますが、本当は違う意見を持っているのに、無理矢理あることを支持する立場で主張させようとしても、的確な批判ができない場合があり、期待するほど機能しません。
5.「はい」や「いいえ」で答えられない質問を問う
勝ち負けを目的にしない対話を導くには、「賛成」や「反対」、「はい」や「いいえ」で答えるテーマや質問を選ばないことです。
ディベートがよい結果をもたらさない大きな要因の一つは、テーマが安易かつ軽率に設定されてしまうことです。答えが限られている場合、議論は浅薄になり、誤解を招くことがあります。
例えば、「AIは社会にとって良いのか悪いのか」と問うのではなく、次のように問いかけるとどうなるでしょうか?
「AIは私たちの幸福にどのような点で役立ち、どのような点で害を及ぼすのか。そして、これらの影響をどのようにバランスさせることができるのか?」
このような問いかけは、参加を分断させるのではなく、共に探求することを促します。
6.多くのことは文脈次第であることを理解し、一般論ではなく具体的な文脈を示す
真実は「文脈」次第です。
つまり、同じ主張でも、ある文脈では正しくて、別の文脈では間違っています。
どちらの主張も、部分的に正しく、部分的に間違っています。
どちらの主張も、真実の一部は捉えていますが、全体を捉えていないことがあります。
ある文脈においては、どちらの主張も間違っていることもあります。
真実の多くは「条件付き」です。
条件によって、正しくもなり、間違うこともあります。
ある点ではプラスになっても、別の点ではマイナス効果になることもあるのです。
例えば「グローバリゼーションは世界にとって良いか悪いか」という質問は文脈が漠然としています。どの国のどの人の立場か、環境にとってか、経済にとってか、人間の幸せにとってか、文脈によって答えは正反対になることもあります。
同様の漠然すぎる質問に「再生可能エネルギーは地球を救うか」や「リモートワークをより普及させるべきか」などがあります。これらの質問は物事を過度に単純に捉えすぎています。
文脈を絞らないと、議論はすれ違ったり、かみ合わずに拡散したり、無駄に対立を煽るだけです。
「どのような状況で、それが成り立つのか?」を問うのです。条件が変われば、結論も変わるからです。
例えば、「パソコン業務主体のIT技術者にはリモートワークは快適さと生産性をもたらすが、現場から離れられない製造や農業の現場では、どうすれば同様の自由さや快適さをもたらすことができるのか」などのように文脈を明確にするのです。
繰り返しますが、ある主張はある条件では正しいかもしれませんが、条件が違えば正しくなくなるのです。そのことを知ってください。
7.共通点を見出す合意形成型対話
お互いの意見が異なる点を探究する前に、たとえ小さなことでも、同意できる点を見つけるのも効果的です。
例えば、
「私たちは皆、テクノロジーが私たちの生活を形作っていることに同意しています。」
「私たちはプライバシーとつながりの両方が重要であることに同意しています。」
「それでは、、、」
こうすることで、相互尊重と協力の基盤が築かれます。
これをマッピングすることも有効です。意見が重なる部分、異なる部分、そして不確実性が残る部分を図示して、視覚的に整理するのです。それによって、問題を争いではなく、システムとして捉えることができます。
8. 振り返る時間を設ける
私たちは、様々なバイアスに支配されています。
討論の参加者は自分自身がバイアスに侵されていないか、認識がゆがんでいないか、自分の思考のプロセスを時々振り返る必要があります。
特にグループの場合は、個人の場合よりも警戒すべきバイアスが増えます。
誤ったコンセンサス(false consensus)、誤った二分法(false dichotomy)、集団思考(groupthink)、集団二極化( group polarization)、集団のコミットメントのエスカレーション(group escalation of commitment)などのバイアスです。
また、私たちには、話しのうまい人を、そうではない人よりも正しいと考えてしまうハロー効果があります。ディベートは多くの場合「雄弁さの大会」になり、話し手の熱量に惑わされます。
私たちは雄弁に話す方法を教えるのではなく、雄弁さに惑わされないことを教える必要があります。
コミュニケーションと討議によって民主主義を刷新できるかを研究するアンドレ・ベヒティガー(Andre Bächtiger)らは、『オックスフォード討議民主主義ハンドブック』の中で、討議は、十分な平等さとお互いへの敬意の条件下で行われるべきであり、参加者が競争するのではなく、内省し、多様な視点を考慮するように促されたときに最も効果的になると主張しています。(3)
探究における認知が規範的民主主義理論に与える影響を研究するミゲル・エグラー(Miguel Egler)は、単に討論を重ねるだけでは、ディベートの構造に埋め込まれた暗黙のバイアス(implicit biase)を克服できず、真実やより良い意思決定が保証されるわけではないと主張します。(4)
むしろ、特定の状況下では、討議が特定のバイアスを増大させることがあることを示しています。議論を重ねても真実に近づくことなく、むしろ、討議によって、アイデンティティや既存のバイアスを強化することがあるからです。
そのため、参加者の多様性、発言の平等性、情報の質や提示の仕方、手続きの公平性といった条件を整えることが重要で、討論の最中にも、これらが維持されているか、特定のパターンに陥っていないかを立ち止まって確認する必要があるのです。
9.意見の相違を創造性へと変える
あらゆる視点を取り入れることで、私たちは意見の相違を創造性へと変えることができます。
協力的で柔軟さがあり、敵対的でない環境で意見を交換する場合、人は意見を建設的に修正できます。そこには「勝者」も「敗者」もいません。学びと成長があるだけです。
何を学んだか。
理解がどのように変化したか。
そして、どのような新たな疑問が浮かび上がったか。
以前紹介したワールド・カフェの原則もそうでした。以下がその原則です。
- 文脈(目的やテーマ、前提)を明確にする
- おもてなしの場、誰もがリラックスして安心して参加できる場を提供する
- 核心的な「問い」を探求する
- 全員の「貢献」を促す
- 多様な見方や考えを結びつける
- 「聞く」ことに集中し、そこに共通するパターンや本質を見つける
- みんなで新しい「発見」をする
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
ふぅ!
以上、ちょっと長くなりましたが、勝つことではなく、理解することを目指す議論の方法を説明しました。繰り返しになりますが、私たちに必要なのは、説得することではなく、相手を理解すること、知識を共有し共創することを志向する対話です。
ただし、すべてのことで合意を目指すのは不可能です。決定を強制することなく、意見の不一致や未解決の疑問点は特定して残してもよいのです。より柔軟に物事を認識し、柔軟に対応しましょう。
そして、常に自分にはバイアスがあることを意識しましょう。
~ ~ ~ ~ ~
参考文献
(1) Emily L. Lilly, “Assigned Positions for In-Class Debates Influence Student Opinions“, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Volume 24, Number 1, 1-5, 2012.
(2) Michael A. Neblo, Kevin M. Esterling, Ryan P. Kennedy, David M.J. Lazer, Anand E. Sokhey, “Who wants to deliberate—and why?”, American Political Science Review, Vol. 104, No. 3, 2010/8.
(3) Andre Bächtiger, John S. Dryzek, Jane Mansbridge, Mark D. Warren, “The Oxford Handbook of Deliberative Democracy”, Oxford Academic, 2018/10/9., accessed 2025/11/15.
(4) Miguel Egler, “Can We Talk It Out?”, Episteme, Volume 21, Issue 3, pp. 837 – 855, 2024/9.



