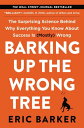人生で一番大切なことは「アライメント」です。成功は、自分が何者であるかと、自分自身が決めた目的との整合性です。そのための第一歩は「自分を知ること」です。その上で、どのような環境に自分を置き、どのような人たちに囲まれるか、人との関係性が大切で、バーカーは、それが達成できれば、それで十分だと言います。
~ ~ ~ ~ ~
間違った木に吠える
今回は、作家エリック・バーカー(Eric Barker)2017年著の『Barking Up the Wrong Tree : The Surprising Science Behind Why Everything You Know About Success Is (Mostly) Wrong(邦題)残酷すぎる成功法則』を紹介します。
「Barking Up the Wrong Tree」は直訳で「間違った木に吠える」、つまり「お門違いの非難をする、見当違いをする」ことを意味するイディオムです。
私たちは、人生を成功に導く要因を誤って捉えることがよくあります。
本書では、次に列記するような、成功に関して私たちが抱く見当違いや疑問を検証し、成功を収める人たちとそうでない人たちは何が違うのか明らかにしていきます。
- なぜ学校で一番になる人が、必ずしも実社会で何か大きなことを成し遂げるわけではないのか?
- お人好しは成功しないのか?利己的な人は成功するのか?
- 人生は冒険すべきか?安全策を取るべきか?
- 途中であきらめる人は成功しないのか?途中であきらめないから成功するのか?
- 自信は成功をもたらすのか?それとも幻想をもたらすだけなのか?
- 外向的に人脈を広げるべきか、それとも内向的にスキルを磨くべきか?
バーカーは、数多くの研究や文献を調査し、そこから得た知見を組み合わせてうまく本にまとめています。
結論がちょっと極端すぎるように感じるところもありますが、それでも、多くの人が、参考になるアイデアや考え方を得ることができることでしょう。
バーカーは、LinkedInのプロファイルで自らを「Grand Poobah(高貴な人)」と名乗っていますが、「バカ殿様」のような意味で使っているのでしょうか。。。
彼のホームページのアドレスも「バカですよ(bakadesuyo.com)」です(笑)。
ひょっとすると、彼の名前が「バーカー」だから「バカですよ」なのかしれません(私の想像にすぎませんが)。
ウイットのあるバーカーの一面を表すととともに、K1やPrideなどの格闘技に絡めた話題も提供するなど、日本に精通した側面も表しているのかもしれません(これも想像です)。
それでは、各章の要点を紹介し、私たちが抱く疑問や検討違いと、それらに対するバーカーの見解を紹介していきましょう。
~ ~ ~ ~ ~
第1章:ルールに従ってプレーするだけでは成功できない
バーカーは、学校の成績がバツグンな学生であっても、その先の人生において革新的な成果を残すことは少ないと言います。
成績優秀な生徒たちは、知的で、良心的で、適合性に優れ、言われたことに従います。
しかし、数学で突出した能力を示していても、さらに数学を伸ばしていくのではなく、得意な数学の勉強時間を減らして、苦手な国語の勉強の時間を増やすように指導され、それに従います。
このような生徒は、その後の人生で組み込まれる社会のシステムの中で、比較的うまく立ち回われるようになるため、多くの親御さんたちが自分の子どももそのように全教科で手堅く及第点を取るバランスの良い大人に成長するよう望みます。
しかし、問題は、学校のように勝敗のルールがはっきりしていて、規則に強く支配された環境で成功する能力だけでは、実社会で大きなインパクトを生むための準備としては十分ではないということです。
これを証明するボストンカレッジの研究があります。
研究者たちが81人の卒業生総代を追跡調査したところ、これらの高学歴を持つ生徒でも、人生に関する先見性を持つことはほとんどないことがわかりました。彼らは決められたシステムの中で最適に動くことはできるのですが、システムに革命を起こすことはできないのです。
学校での成績の良し悪しは、その人が既存のシステムに従うことができるかどうかを示す、信憑性の高い予測材料にはなります。しかし、学業には明確な判定基準がありますが、人生にはそれがありません。そのような基準がない環境下では、ルール従属者たちは優位性を失うのです。
逆に、世界で最も成功する人たちは、既存のルールに従うことを重んじず、情熱に突き動かされ、宗教的なまでの美徳をもって自らの信念に従い、自分のプロジェクトに打ち込みます。しかし、他方ではいい加減だったり、適当だったりして、学業では良い成績を収めないことがあります。
フォーブス誌の400人のリストのうち58人は、大学を中退しているか、あるいは大学にすら行っていません。
しかし、この58人の学業不振者たちの純資産額は、400人の中でアイビーリーグの学校に通っていた他の人たちの平均資産額の2倍以上にもなっているのです。
指導者には2つのタイプが存在します。
既存のルールを通して「フィルターにかけられた」結果リーダーとなった指導者と、そのような「フィルターにかけられていない」リーダーです。
「フィルターにかけられた」リーダーはボートを守り、「フィルターにかけられていない」リーダーはボートを揺らします。
どちらにも、一長一短、適材適所があり、あらゆる場面でどちらだけが常に優れることは決してありません。
しかし、社会では、時にボートを揺らすことが求められます。「フィルターにかけられた」リーダーは、ボートを揺らすことができず、革新性という点では能力が劣るのです。
問題なのは、社会では、フィルターにかけられたリーダーが万能だと、多くの人たちが勘違いしていることです。フィルターにかけられたリーダーたちでもボートを揺らすことができると思っているのです。
そして、フィルターにかけられていないリーダーは、その突出した能力を活かしきれないだけでなく、不当に抑圧されたり、色眼鏡をかけて見られてしまうことです。
しかし、フィルターにかけられたリーダーが「優れたリーダー」となる一方で、「偉大なリーダー」になるのはフィルターにかけられていないリーダーの方です。両者の違いは「どちらがより○○だ」というような問題ではなく、人として根本的に違うということです。
実は、今の世の中では、リーダーには「フィルターにかけられた」能力と「フィルターにかけられていない」能力の両方を併せ持つことが求められています。
以前、「パラドックス・マインドセット(Paradox mindset)」あるいは「アンビデクテリティ(Ambidexterity)」と紹介しましたが、日本語では、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授が訳をあてた「両利きの経営」が有名です。
しかし、現実では、このような両方の特性を併せ持つリーダーはとても限られています。
リーダーには「自分を知る」ことが望まれます。
何が自分が得意で、何が不得意かを知るのです。そして不得意な分野は、自分より優秀な人たちに任せ、自分は得意な分野に集中するのです。
これはとても重要で譲ることができない原則ですが、多くのリーダーには「自分より優秀な人たちに任せる」ことどころか「自分より優秀な人たちがいる」事実自体を認めることができないのです。
~ ~ ~ ~ ~
第2章:「いい人」は、頂点に立つか、底辺で終わるかのどちらかをたどる
単なるいい人、馬鹿正直な人は人に利用されて終わります。
反対に、他人をだまし利用する不誠実な人間は、短期的にはその悪質さを見抜かれず、逃げ切ることができます。しかし、その行動を繰り返すうちに、次第に不誠実さが人に知れ渡り、人を遠ざけ警戒させるので、長期的に成功することはありません。
馬鹿正直な人は成功できない、不誠実な人も長期的に成功できないのであれば、私たちが成功するにはどうすればよいのでしょうか?
人と協力すること、誠実であることは絶対必要です。
しかし、もし人に裏切られたら、その人を裏切り返さなければなりません。
以前、本サイトでゲーム理論の「囚人のジレンマ(prisoners’ dilemma)」を紹介しましたが、バーカーも本書で引用しています。
「囚人のジレンマ」とは、「協力した方がしないよりもお互い良い結果を得ることが分かっている状況でも、相手を裏切った方がより多くの利益を得ることができる状況では、互いに協力しなくなる」というジレンマで、ゲームを1回行う場合は相手を裏切ることが合理的なのですが、私たちの人生のようにゲームを無限回繰り返すような場合は、自分から裏切ることはせずに相手と協力するというのが、このゲームの最強の戦略になります。
「tit for tat(しっぺ返し戦略)」と呼ばれる有名な勝利の戦略があります。この戦略では、相手を信頼し、自分から裏切ることは決してしません。しかし、相手が裏切ってきた時は裏切り返すのです。
親切、誠実であることはとても重要ですが、同時に人がよすぎてもだめだということです。
聖人である必要はないのです。
悲しいかな、この世の中には悪い人ばかりとまでは言わなくても、人をうまく利用して自分の利益にしようとする人たちがあふれています。そのような人たちに盲目的に仕え続ける誠実でバカ正直な人たちは、結局いいように使われたり、搾取されて終わってしまうのです。
あなたがそのような人たちにもし搾取されているのであれば、反撃しなければなりません。そうしなければ、あなたは搾取され続けて終わるのです。
また、長期的には、そのような人たちとの付き合いは断ち切るか、断ち切れない場合は付き合いを最小限にして、誠実な人たちと協力し続けることができる環境を自ら構築することが大切です。
~ ~ ~ ~ ~
第3章:成功者は決してあきらめないのか?強い目的を持つことで、つらい経験も乗り越えられる
以前、1944年にアウシュビッツに収監された心理学者ヴィクトール・フランクル(Viktor Frankl, 1905 – 1997)が1946年に書き、世界中でベストセラーとなった書籍「Man’s Search for Meaning(邦題)夜と霧」を紹介しました。
収監中、フランクルは、収容所で他の人たちよりもずっと長く生き延びている人たちの存在に気が付きます。
そして、地獄の苦しみの中でも生き続けているのは、その人たちが人生に意味を見出し、持ち続けているからだと知ります。フランクル自身も生存者ですが、彼も収監中、妻のために生き延びたいと思い、いつも想像の中で妻と会話をしていました。
つまり、どんな厳しい経験でも、あるいは逆につまらないことでも、人生の目的を強く持ち、尊厳をもって立ち向かうことで、私たちはどんな逆境も乗り越えることができます。
これは、自殺という真逆の事例においても当てはまります。
アメリカの社会心理学者ロイ・バウマイスター教授(Roy Baumeister)によれば、自殺した人たちは最悪の境遇にあったわけではなく、自分自身の期待にかなう境遇に恵まれなかったことに不遇を憂えたため、自ら命を絶ったのだと言います。
これは、自ら人生に目的を掲げる人と、誰かに人生の目的を与えてくれるのを期待する人の違いなのです。
~ ~ ~ ~ ~
第4章:外向的な人は最もお金を稼ぐが、最高の専門家は内向的な人が多い
高校のクラスで最も人気のある20%の生徒は、最も人気のない20%の生徒よりも就職してからの収入が10%多いという研究結果があります。
また、外向的な人は飲みに行ってお金を使う傾向が強いが、他の人と親しくなって、貴重な人脈を形成する可能性も高く、酒好きの人の収入がシラフの人より10%多いという研究結果もあります。
このように外交的な人が成功する一方で、専門性を極めていくことで成功する可能性が高いのは内向的な人たちの方です。
作家でオリンピックメダリストのデビッド・ヘメリー(David Hemery)が行った調査によると、トップアスリートの89%が自分を内向的だと考えており、外向的だと認識しているのはわずか6%にすぎませんでした。
どんな分野であれ、どんな人であれ、優れた専門家になるには、練習や勉強に1万時間以上費やすことが必要であると知られていますが、簡単に言えば、外向的で人付き合いを好む人には、専門知識を身につけるために必要な膨大な時間が残されていないのです。
~ ~ ~ ~ ~
第5章:成功と自信の関係性
研究結果によると、概して、自信のなさは成功から私たちを遠ざけ、自信がある人は困難な仕事に挑戦し、自分の道を切り開き成功に近づいていきます。
しかし、自信過剰な人は、自分を肯定的に捉えられる一方で、現実離れした幻想や傲慢さを引き起こし、悲観的な人の方が、現実を見据えた適切な意思決定ができ、成功する可能性が高いという研究結果もあります。
つまり、自己肯定と自己否定、楽観主義と悲観主義は一長一短があります。
そこで、著者は「セルフコンパッション(self-compassion)」のコンセプトを持ち出しています。
以前本サイトでは、アメリカの臨床心理学者カール・ロジャーズ(Carl Rogers)の「ありのままの自分を受け入れるから成長できる」、「噓偽りがないありのままの自分の全体的な感覚が、最も信頼できる」という教えを紹介しました。
また、世界的なスピリチュアル・リーダーエックハルト・トール(Eckhart Tolle)の「今に意識を集中し、自分をただただ知ることで、完全に目覚めることができる」という教えを紹介しました。
自分の考えや感情を抑制したり否定したりすることなく温かい態度で観察するセルフコンパッションも、これらに通じるコンセプトです。ただし、この章では筆者のバーカーは彼の主張を表現するのにセルフコンパッションを重ね切れていない感があり、個人的にはピンとこない章になっています。
~ ~ ~ ~ ~
第6章:成功の鍵は、成功を自分自身がどう定義するかによる
以前本サイトで、ハーバードビジネススクールのローラ・ナッシュ(Laura Nash)とハワード・スティーブンソン(Howard Stevenson)が提唱した、個人の持続的な成功に欠かせない次の4つの要素を紹介しましたが、バーカーも全く同じ引用をしています。
1.幸福(Happiness):人生に対する喜びや満足感
2.達成(Achievement):自分が設定した目的の達成感
3.重要(Significance):自分が大切に思っていることに良い影響を与えている感覚
4.貢献(Legacy):人の未来への手助け
今の世の中では、他のことを犠牲にしてでも、あることを極めたり、多くのモノや成功を手に入れたり、華々しく送る人生が美徳だと捉えられているように感じます。
しかし、上を見続けることにはキリがありません。「十分(good enough)」を知ることが大切です。
上の4つの要素でバランスを取り、それぞれに対して、「自分にとっての十分」を設定するのです。
自分の人生の目的を決めるのは、他人ではなく自分です。
人生の目的は、人から与えられた選択肢から選ぶのではなく、自分自身が設定するのです。他人の成功をコピーするのではなく、人と比較するのでもなく、自分で生み出すのです。自分が何のためにどこに向かっているのか知らなければ、時間を有効に使うことさえもできません。
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
バーカーは人生で成功する上で一番大切なことは、ただ一言「アライメント」だと言います。
成功は、1つの物差しで測った結果ではなく、自分が何者であるかと、自分自身が決めた目的との整合性です。さらにはその上で、どのような環境に自らを置き、どのような人たちに囲まれるか、人との関係性が大切で、バーカーはそれで十分だと言います。
そのためにはまず「自分を知ること」が第一歩になります。
「自分を知ること」は古代ギリシア時代から、表現を変えて、数多くの偉人たちによって繰り返されてきた言葉です。長きにわたり繰り返し説かれているのは、それが人生の成功の本質を示す言葉だからです。
良いところも悪いところも含めて、噓偽りのないありのままの自分を知ることです。