前回、前々回と、難しい会話の対処方法を紹介しました。今回はそれでも会話を築くことができない「恐ろしく難しい人」の対処方法を紹介します。ポイントは、相手を変えようとする意識を捨て、相手を理解することに努め、決して相手の土俵に乗らず、自分の行動を変えることです。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
会話は2人以上で成立するものなので、あなた1人だけの努力で必ずしも改善できるものではありません。
ネガティブなオーラに包まれ、否定否定のオンパレード、会話するのがとにかく難しく苦痛な相手はいたる所に存在します。気難しい人との交流は、私たちから、エネルギー、生産性、さらには幸福感を奪い、大きな負の影響を及ぼします。
欧米など5,000人のオフィスワーカーを対象とした調査によると、その85%もが職場で何らかの人間関係のコンフリクトを抱えていました。(1)(2)
もちろんコンフリクトは、職場だけではなく、家族や交友など、社会のあらゆる人間関係で起きます。
以前、人と人とのコンフリクト(意見の違い)が人や組織の成長を促すと書きました。しかし、恐ろしく難しい人にあるのはもはや健全なコンフリクトではなく、敵対心と行き過ぎた防御心です。そのような人とはどうしても会話の前提となるまともな2方向のコミュニケーションが成立しません。
このような人たちは明らかに組織に有害なのですが、残念ながら日本の組織の仕組みや人事制度では簡単にいなくなってもらうこともできません。今回は、そのようなとても難しい人に対応する方法を紹介します。
~ ~ ~ ~ ~
恐ろしく難しい人のタイプ
一言で恐ろしく難しい人と言っても、さまざまなタイプがあります。以下はその一部の例です。
1.他人を蹴落としてでも、自分のアピールに全力を尽くす人
人の成果を横取りするのはまだかわいいレベルです。
自分の忙しさをアピールするためだけに、午前3時にメールを送ってきたり、日曜日にメールを送ってくる人、情報を囲んで共有せずマウントを取る人、他人の評価を相対的に下げるため、人の悪口やうわさを広げる人、自己防衛と責任転嫁のために、破壊的な行動をも厭わない人もいます。
他人の時間をやたらと取る割には、のらりくらりと仕事をして、ギリギリになってから仕事を振ってきて人のせいにする人たちもいます。
2.自分の弱みから逃げるため、核心に迫らせない人
このような人は、とにかく話をややこしくします。
あなたが理解できないのは当たり前です。なぜなら、問題の核心に迫る会話に迫らないように、意図的に話をずらしたり、煙に巻いたり、物事を理解させないように説明するからです。
皆さんのまわりにも、何回聞いていも話の中身が理解できない人がいませんか?
そのような人はわざと分からないように説明している可能性があります。
表面的な体裁を整え、責任を回避するために、話を誇張したり、うそをついたり、意味のない話を長々したり、物事をかき回したりして、やってる感を演出します。
3.人を巻き込んで、責任をなすりつけようとする人
常に人をいらいらさせようとする、二者択一を迫ってくる、罠に引きずり込もうとする人たちです。その巧みな仕掛けのために、知らないうちにあなたの責任にされることがあります。
他人を怒らせておいて「そんなに怒らないで下さいよー」とか「なんでそんなに怒ってるんですか?」と感情の責任を押し付けてきます。
4.自己を維持するために自分をも欺く人
これは最上級に難しいタイプです。
アメリカの精神科医で作家であるスコット・ペック(Scott Peck)は、「人の形をした悪魔(Human Evil)」と呼びます。(3)
以前、彼の著書『People of the Lie(邦題)平気でうそをつく人たち:虚偽と邪悪の心理学』を読んだとき、私は全身に寒気が走りました。
この種の人は、罪悪感を回避し、完璧な自己イメージを維持するために、他人に嘘をつくだけでなく、自分自身にも嘘をつくことができます。自分についた嘘を完全に内面化しているので、自分では嘘をついているという意識はまったくありません。
ある特定の人をターゲットにし、スケープゴートにして破壊していきますが、周囲の人たちから見ても、その異常さに全く気が付きません。むしろ、社会的には優秀で高く評価されたり、愛にあふれていると認識されていることさえあります。
以上4つのタイプ以外にも、まだまだ多くのタイプがありますが、深入りするとメンタルに良くないので、もうやめましょう(笑)。
少なくても、恐ろしく難しい人は、あなたがまともだと思う理論、正論、常識は通用しません。敢えてずらしているからです。そして、本当に難しい人間はとても巧妙です。その点ではプロ級です。話のつなげ方もうまく、一般の人では何の疑いもなく受け入れてしまいます。気が付いたら信じ込まされています。その巧みさにおいては、善良なあなたは足元にも及びません。
感情的になったらあなたの負けです。
こちらも考えを変えなければなりません。以下は、難しい人に対峙するポイントです。
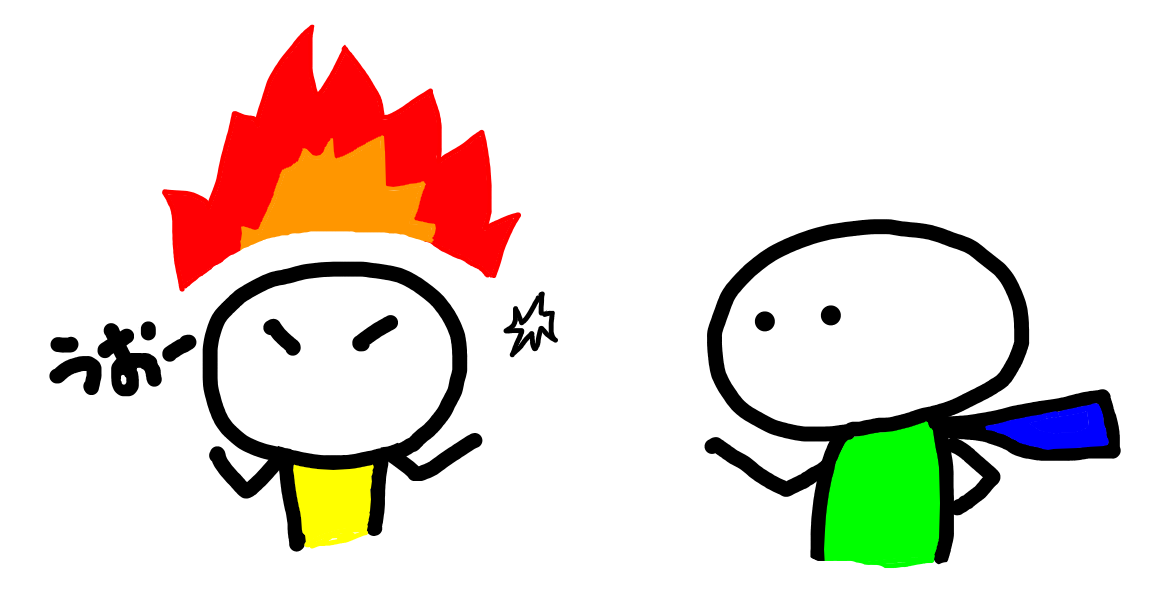
~ ~ ~ ~ ~
難しい人の対処仕方
1.相手を変えようとする意識を捨てる
まず、相手に何かを理解させたり、説得したり、コントロールしようとする一切の意識を捨てましょう。理屈や道理が通じる相手ではありません。
変えなければならないのは、あなた自身であり、相手ではありません。
自分の考え方を伝えることはあっても、それを押し付けてはいけません。判断の責任は相手に持たせます。それ以上のことをする必要はありません。
あなたは誤解されたり、嫌われることを心配するかもしれませんが、気にした途端、相手にペースを奪われます。そのような人に認められる必要はありません。嫌われて大いに結構です。
相談したり、提案したり、指示した途端、相手はその責任をあなたに押し付けてくるので、不用意に、何かを相談したり、提案もしないでください。
例えば、感情的になって騒いでいる人に「静かにしなさい、落ち着きなさい」と言っても、状況が収まらないだけでなく、知らない間にあなたがその場の責任を引き受けてしまいます。「静かにした方がいいと思うよ」など意見だけを伝え、相手の行動の責任は相手にあるままにしておくのです。
必要な場合は、あなたの思いや考えに基づいてではなく、明確なルールに則って相手を縛ります。
2.相手の理解に努め、なぜそういう態度や行動を取るのかその動機を考える
大切なのは相手の人格を非難することではなく、相手の考えがどこから来ているのか、相手が置かれている状況に目を向けることです。
「どうしてそう考えるんだろう」と相手の立場になってその動機を冷静に様々な角度から考えてみてください。そのために相手に質問をする必要がある場合は、とげのない思慮深い言葉を選ぶよう細心の注意を払いましょう。
そうすることで、相手と自分が見ている事実が違うことに気が付くかもしれません。個人的な事情や、置かれた状況、物の見方が違うかもしれません。そのために不安に駆られたり、何か避けようとして躍起になっているかもしれません。その動機が、あなたに対する言動に繋がり、特定の行動として現れていることが分かるかもしれません。
相手の理解に徹することはあなたを謙虚にします。
コミュニケーションのコツとしては、声を荒げたり相手を見下した言い方をしない、穏やかに話す、相手が一息つくまで待つなどです。
相手を理解したいと思い、理解に徹することです。そうすれば、自然と感情は抑えられるはずです。
3.自分の意識と行動を変える
繰り返しになりますが、難しい相手との関係において変えることができるのは、あなたの意識と行動だけです。よくありがちな間違いは、相手の文句ばかり言って、自分の考え方や行動を変えないことです。相手の文句ばかり言っていては、一生かかっても問題は解決できません。
あなた自身が行動を変えないのなら、ある意味、あなたも問題に加担しています。自分は間違っていないという考えから抜け出せないあなたも問題なのです。
それを克服するためには、自分の対応の間違いが明らかになったら素直にそれを認め、その間違いを取り除く行動を相手に求めるのではなく自分が実行するのです。
4.自分と相手の間に十分な距離を取り、決して相手の土俵に乗らない
あなたを悩ませる問題人物が赤の他人であれば、全く関わらないという選択肢もありますが、残念ながら、仕事の関係などで、全く無関係でいられないこともあるでしょう。そんな状況でも相手と適度な距離を取るのが大切です。
難しい人が声を荒げると、ついつい怒鳴り返したり反論したくなりますね。しかし、それでは相手の思うつぼです。相手が「近寄って来い」とメッセージを送ってきていて、あなたは近寄ってしまっているのです。
難しい人は巧みに2人の間のフェンスを乗り越え侵入し、あなたのロジックを壊し、自分の土俵に引き込もうとします。大量のメールやメッセージを受け取るかもしれませんが、いちいち反応する必要はありません。そんな人に嫌われることを恐れてはいけません、そもそもすでに本心では嫌われていますから(笑)。
嘘つき呼ばわりされたり、悪者扱い、誹謗中傷されても、その撒かれた餌に近づかず、感情的にならず、逆に距離を取って、必要以上のことは話さず、安易に同意もしません。冷静さを保ち、相手の話を聞く事に集中し、嵐が去るのを待つのです。
日本でも「心の知能指数」や「感情知能」として紹介されることが増えてきた「エモーショナル・インテリジェンス(Emotional Intelligence : EQ)」で引用される言葉に「アパテイア(apatheia)」があります。(4)
「アパテイア(apatheia)」はもともと哲学用語で、感情に邪魔されない心の状態です。アパテイア(apatheia)は、無関心(apathy)ではなく、平静な状態を意味します。
感情的に他人に近づきすぎて影響を受けたり(巻き込まれ型)、世界から完全に離れる(解離型)のでもなく、他人と距離を取るものの、世界の秩序の一部にある状態です。この2つの状態の間にあるスイートスポットを見つけることができれば、外の世界で起きることから悪い影響を受けず、満足感と良い感情を維持できるのです。
5.結局すべての問題を解決できるわけではない
あなたは、すべての問題を解決できるわけではありませんし、すべてに責任があるのでもありません。すべてに責任を感じる必要もありません。
聖徳太子やブッダでさえ全ての人に対応できたわけでなく、全ての問題を解決できたのでもありません。あなたは聖人でも偉人でもなく、一般人です。
考えられる限りのことをした結果、満足できなくても、自分を責めないことです。相手の問題を自分の問題にしてはいけません。あなたの仕事は、他人の問題を引き取ることではありません。
「The HBR Guide to Dealing with Conflict」の著者であるエイミー・ギャロも、どんなにあなたが頑張ろうが対処できない人は必ずいて、それは仕方がないことだと述べています。
時々人はあなたに怒り狂うでしょう。。。それでOKです。
~ エイミー・ギャロ
Sometimes people are going to be mad at you … AND THAT’S OK.
~ Amy Gallo
難しい人と対峙すると、ものすごいエネルギーを奪われます。そのストレスがパフォーマンスを下げるだけでなく、そのために心と体まで害してしまってはあまりに不条理です。一線を引き、それ以上の努力はしないことです。
あなたのそのエネルギーを、自分や家族のため、世界平和、社会貢献などもっと有意義なことに使ってください。

~ ~ ~ ~ ~
最後に
チベット仏教に「トンレン(Tonglen)」という言葉があります。
誰か嫌な人や苦手な人と対峙した時にも利用できるもので、痛みや混乱を感じた時に、その感情、質感、匂いのすべて、更には相手の痛みも含めたすべてを息を吸うように受け入れ、息を吐き出してそれを自由にします。(5)
自分と他者の苦しみを受け入れ、息を吐き出すときに幸福を与えるイメージですが、ただ単に、息と共に感情を大きく吸い取り、ゆっくり吐き出して解放するだけでも確かに楽になる気がします。
最後にポイントを簡潔にまとめました。
- あなたの前提を捨てる
- 相手の良し悪しを判断しない
- 相手に興味を持ち、 聞き、理解することに集中する
- 相手の人格、人柄ではなく、背景、関心、動機、意図、課題とその捉え方を理解することに集中する
- 感情に感情で返さない。落ち着き、冷静でいる
- 沈黙を利用する
- 売られたけんかを買わない
- 相手の土俵に乗らない。嘘には真実で返し、否定には肯定で返す
- 限界点を設定する。あなたは全てを解決できる訳ではない
- 深呼吸して気持ちを楽にする
皆さんも恐ろしく難しい人に人生を振り回されないように、変えられないことは変えられないと割り切って対応していきしょう!
~ ~ ~ ~ ~
参考文献
(1) “CPP Global Human Capital Report – Workplace Conflict and How Business can Harness It To Thrive“, CPP, Inc., 2008/7.
(2) Scott Mautz, “6 Ways to Gracefully Handle the Most Difficult People in Your Life Co-workers or any difficult people in your life don’t have to cause you so much angst“, Inc., 2019/10.
(3) M. Scott Peck, “People of the Lie”, Touchstone, 1998/1.
(4) Drew Bird, “Emotional intelligence: How to work with people you don’t like“, The Enterprisers Project, 2019/6.
(5) Pema Chödrön, “Living Beautifully: with Uncertainty and Change”, Shambhala, 2012/10.
(6) Karen Young, “Toxic People: 16 Practical, Powerful Ways to Deal With Them“, Hey Sigmund
(7) Karen Young, “Toxic People: 12 Things They Do and How to Deal with Them“, Hey Sigmund
(8) Barbara Markway, Reviewed by Lybi Ma, “20 Expert Tactics for Dealing with Difficult People“, Psychology Today, 2015/3.





