私たちは皆、人生を最大限に生きたいと願っています。しかし、目の前に妖精が現れ、魔法でそれを実現してくれることはありません。たとえ実用的な成果を生み出さなくても、結果にとらわれず、好奇心に導かれ、心惹かれるものに飛び込んで、小さな実験を繰り返すことで、その魔法が見つかるのです。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
アンヌ=ロール・ル・クンフ(Anne-Laure Le Cunff)は大学卒業後、誰もが憧れるキャリアを突き進んでいました。
グーグル本社での夢のような仕事、スキルとマッチしたチャレンジングな業務、高い給料、素晴らしい福利厚生、面白い同僚たち、様々な国への出張。
グーグルでは、すべてのプロジェクトに明確な目標があり、すべてがデータによって判断され、昇格に必要なスキルも誤解の余地がないほどはっきり示されていました。
ル・クンフは、そこでデジタルヘルス事業に携わります。
与えられた以外のプロジェクトにも積極的に関わり、必要であればプライベートの用事をキャンセルしてでも仕事を優先しました。
転機となったのは、医師が彼女の腕に血栓を発見し、それが肺に転移する可能性があると診断した時です。彼女はすぐに手術を受けず、プロジェクトチームに迷惑をかけない日にちまで先延ばししました。
手術は無事に終わり、すぐに業務に戻ります。
しかし、彼女の中で何かが変わっていました。
若い頃、彼女は好奇心に導かれて様々なことを試し、学び、成長してきました。しかし、グーグルでは今後身に付けるべきスキルやたどり着くべき目的地、そこまでの道のりがまっすぐに定められていました。
仕事は素晴らしいものでしたが、彼女の深い意味や価値観とずれが生じてきていました。
「なぜ私は外面的にはとても成功しているのに、心の中はこんなにも平らなのだろうか?」
「これが私の望む人生なのだろうか?」
アンヌ=ロール・ル・クンフは、悩んだ末に27才にして誰もが憧れた会社を去る決断をし、ヨーロッパに戻ります。
そこでヘルスケアのスタートアップを立ち上げますが、また同じことの繰り返しです。
数えきれないほどのピッチトークをし、目が回るくらい忙しい日々を過ごし、結局事業を軌道に乗せることができずに会社を閉じることになります。彼女は疲れ、燃え尽き、完全に道を見失っていました。
その後しばらく、何の制約も締め切りもない生活に戻ると、働き始めてから長く失われていた感覚が少しずつ戻ってきます。
「好奇心」です。
彼女は目的地が定まった決められた道を進むのではなく、好奇心に任せて行動し、かつての自分を取り戻していきます。
文章を書き、日記をつけ、心の仕組みについて考えるようになりました。学習への興味が芽生え、脳科学を勉強するために学校に戻ります。単なる癒しではなく、学びを他人と共有したいと思い、ブログを書き始め、自分のホームページを立ち上げます。そして、それが小さなビジネスになります。
~ ~ ~ ~ ~
目標にとらわれた世界で自由に生きる方法
今回紹介する書籍は、2025年3月に出版された『Tiny Experiments: How to Live Freely in a Goal-Obsessed World(邦訳)小さな実験:目標にとらわれた世界で自由に生きる方法』です。なお、現時点では日本語版はありません。
本のタイトルから、この本は、彼女のように、生産性至上主義、上昇志向の強い人、目標にとらわれた人たちを対象に、自由に生きるためのアドバイスをしているように見受けられるかもしれせまん。
しかし、彼女のように毎日忙しい人がふと立ち止まって人生のあり方を見つめなおすようなケースでなくても、さまざまな人たちにさまざまな場面で参考になる書籍です。
例えば次のようなケースです。
- 何か新しいことを始めたいが、どうしたらよいかわからず先に進めない人
- 目標を設定しても、なかなか実行に移せない人、長続きしない人
- 目標を設定したが、その目標にピンとこない人、心と体がついてこない人、充実感が感じられない人
- どんな目標を立てればよいのか分からない人
- 出世の階段を昇ることに疲れた人、会社の仕事に意味を見出せなくなった人
- 計画通りに物事が進まなくて悩んでいる人
- 人生や仕事の谷間に陥った人
~ ~ ~ ~ ~
小さな実験 Tiny Experiment
私たちは、ある時、ダイエットを始めようと一念発起します。英語の勉強を毎日続けようと決心します。朝のランニングを始めようとします。しかし、その決意は長続きせず、イライラし、あきらめ、落ち込み、自分に失望します。
脳は、脳科学者が「知覚行動サイクル」と呼ぶサイクルを通して機能します。
私たちは身の回りの情報を知覚し、予測を立て、その予測に基づいて行動を起こします。そしてその結果を用いて将来の予測精度を高め、行動の効率性や確度を徐々に高めていきます。
このサイクルを反復することで、私たちに「スクリプト」が形成されます。スクリプトとは、無意識のうちに私たちを導く内面化されたルーティンです。このルーティンに基づいて、意思決定と実行をより少ないエネルギーで無意識かつ高速にできるようになります。
一方でこのスクリプトから外れた、全く新しい行動を取ることは難しくなります。
私たちの脳は効率性を重視して作られているため、ある行動を最適化する一方で、好奇心を押し殺し、新奇なもの、不確実なものを避けるようにもなるのです。
好奇心が抑圧されるのは、個人的な要因だけでなく、社会的な要因もあります。
社会は、ある特定の行動を効率的に行える人を高く評価します。決められた役割を果たし、特定の結果を達成できる人が優秀と見なされます。一般に、好奇心があるだけの人や、それゆえにその人が持つ新しいアイデアを生む力は評価されません。
つまり、私たちは個人的な面からも社会的な面からも、ある行動の効率性を得ると共に、新しい行動の可能性を失っていくのです。今までの習慣と異なる新しい行動を始めることは、様々な意味で大量のエネルギーを必要とし、ハードルが高いのです。
だからこそ、私たちは意図的に探索のための時間を作る必要があります。たとえ実用的な成果を生み出さなくても、心惹かれるものに飛び込んでみたり、興味を引かれたランダムなトピックを探求してみるのです。
ル・クンフは、体に染みついた習慣に捉われず、好奇心に自分を導かせて、何でも一度やってみればいいと言います。これを小さな実験(Tiny Experiment)と言います。
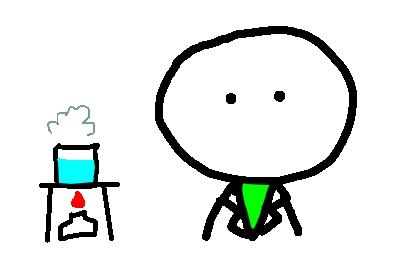
~ ~ ~ ~ ~
PACT
小さな実験とは、自分自身と行う、小さくてリスクや不安の少ない「約束」です。
何かを達成するためのものではなく、何かを検証するために自分自身と交わす約束です。
本書では、小さな実験を行う具体的なステップとして「PACT」を提唱しています。PACTは、次の4つの言葉の頭文字を取ったものです。
1. Purposeful:目的
- 「なぜ自分はこれをやりたいのか?」自分自身に問いかけましょう。
- 実験は、誰かからのプレッシャーによるものではありません。社会や周囲からの期待に応えるものではなく、自分自身の純粋な好奇心、興味による実験です。
- 目的は、「達成度」でも「数値目標」でもありません。「○○までに□キロやせる」ではありません。結果よりもプロセスが大事です。
- 例えば、「寝る前のストレッチが、睡眠の向上に役立つか試してみたい」とか「スマホから1日1時間完全に離れることがどう役立つか試してみたい」など、ちょっとした目的でよいのです。
2. Actionable:実行可能
- 抽象的なものではなく、すぐに実践可能なもの、日常生活に組み込めるもので、できるだけシンプルにしましょう。始める前に「大変だ」と感じたら、大きすぎです。
- 「もっとマインドフルネスになる」は実行可能ではありません。動詞を使ってください。
- 例えば、「毎朝5分間頭に浮かんだことを書いてみる」とか「寝る前に5分間ストレッチする」などです。
- 繰り返しますが、自分自身の好奇心、価値観、興味と合致していることが大切です。
- 完璧さを求めないこと。進歩は、小さく不完全な一歩から始まることが多いのです。不完全とは、ずさんさではなく、戦略的な緩さです。準備を周到にしないでください。完璧主義者は開始を遅らせます。
3. Continuous:継続可能
- 「私は○○を□□の期間行う」という約束を自分とします。続けられるか不安になるほど長い時間を設定する必要はありません。「次の1週間、週3回、朝起きたら外に出て深呼吸する」でもよいです。
- 一度きりの結果にこだわるのではなく、繰り返しと持続性を重視しましょう。
- 「意志の力で燃え尽きることなく、継続してできることは何だろう?」と考えてみましょう。
4. Trackable:結果の振り返り
- 実験の結果を振り返ることができるようにしましょう。軽い振り返りで十分です。
- PACTは実験です。実験から得るのは合格・不合格という結果ではありません。「成功したか?」ではなく「何を発見したか?」かです。
- PACTはSMARTやKPIのような目標管理でもありません。、目標未達成という結果はあり得ず、そのため、罪悪感や自己批判もあり得ません。どうだったかをただ振り返るのです。
- 振り返る際は、外的なシグナル(状況、リソース)と、内的なシグナル(やる気、感情)に耳を傾けましょう。
- 実験から何らかの学びを得るはずです。それを明らかにしましょう。「特になにもなかった」も新たな発見です。成果でなく、学びを祝福し、それを次のPACTのループに生かすのです。
例えば次のような感じです。
P:朝の集中力を高める
A:毎朝1分間だけ意識して、今日意図的にやってみる1つのことを決める
C:それを7日間続ける
T:何か変化があったか書き留めてみる
何かに興味が湧いたら、それを遊び心のある小さな実験に変えてみましょう。
決して計画を大きくしてはいけません。
人は計画を立てている時、自分は何でもできると思いがちですが、自分の能力を過大評価し、必要な時間や労力を過小評価します。実行可能だと確信できるほど小さく、短い期間にすることが大切です。
小さな実験を行い、それを振り返ることで、抽象的な好奇心が実践的な発見へと変わります。
既存概念を取り除き、変化した価値観に沿って意思決定を行うことができます。
成功とは、何か新しいことを学ぶことです。真の目的は、固定された計画からではなく、継続的な探求と内省を通して生まれるのです。
小さな実験の結果を振り返る際に有効なのが、「プラス / マイナス / ネクスト(Plus/Minus/Next)」です。
- プラスとは「何がうまくいったか」で、
- マイナスとは「何がうまくいかなかったか」で、
- ネクストとは「では次にどうするか」です。
繰り返しになりますが、大きな変化は必要ありません。ただ好奇心を持って日々の生活や仕事にあてはめるのです。それが小さな実験の目的です。
~ ~ ~ ~ ~
PACTとアジャイル
PACTは、システム開発やソフトウェア開発等で利用されるアジャイルに似ています。
アジャイル開発は、当初は予測できない仕様の変更が将来起きるという前提で、初めから詳細に設計せず、最小限の仕様で開始する開発手法です。小単位かつ短期間で作業をおこない、そこで得た新たな発見を次の反復のインプットにして改良を繰り返していきます。
PACTは、「アジャイル型の人生開発」とも言えます。
学習が成長の原動力となる成長マインドセットとも共通します。
~ ~ ~ ~ ~
PACT ➡ ACT ➡ REACT ➡ IMPACT
本書では、「PACT → ACT → REACT → IMPACT」というループも提唱しています。PACTが小さな実験ループだとすれば、このループはそれよりも少し大きな成長のループです。
PACT:小さな不完全な行動を設定する
ACT:たとえ雑然としていても、試してみる
REACT:Plus/Minus/Next などのツールを使って振り返る
IMPACT :調整して繰り返す
このモデルは、以前本サイトで紹介したダブルループ・ラーニングに似ています。
ダブルループ学習(double-loop learning)とは、システム思考の草分け的存在であるクリス・アージリス(Chris Argyris, 1923 – 2013)が提唱した理論で、同じやり方を繰り返し続ける(シングルループ)だけでなく、時々そのループの前提を見直して、必要に応じてそのループに変化を与えるプロセスを追加することです(ダブルループ)。
ダブルループ学習は、前提を批判的に見るモデルである一方で、「PACT → ACT → REACT → IMPACT」は批判的というよりは、好奇心や創造性を成長のループにつなげていきます。
しかし、共に内省、メタ思考、気づき、学びを促進し、反復を改善と成長につながる点で共通しています。
~ ~ ~ ~ ~
好奇心とインテグリティ
本サイトの前回、前々回の記事で、インテグリティ(誠実さ)を紹介しました。
折角なので、好奇心とインテグリティの関係も考えてみましょう。これらは共存するのでしょうか?
インテグリティ(誠実さ)と好奇心は、一見相反するもののように思えるかもしれません。
1つは自分の信念や価値観に根ざし、もう1つは未知の世界を探求することです。
しかし、この2つは共存可能で、共存するとむしろ、力強い内面の調和が生まれます。
前回紹介したリーバイス社前CEOのチップ・バーグ(Chip Bergh)も、インテグリティを貫きながら、イノベーションを導きました。原則にぶれがないことと、自由な発想は相容れるのです。
インテグリティは、道徳観に基づいた好奇心をもたらします。好奇心が、他人の幸福や社会の健全性を損なうことに使われないことを保証します。
インテグリティは静的なものではなく、真実、自分、他人に対する理解を進化させます。好奇心は、自分の思い込みを疑い、深く耳を傾け、自分にとっての誠実さの意味を時間をかけて洗練させていく力となります。
つまり、好奇心を通してインテグリティは深化するのです。
誠実さを欠いた好奇心は、無謀になったり、操作的になったりする可能性があります。
好奇心を欠いた誠実さは、独断的になったり、閉鎖的になったりする可能性があります。
バランスが取れていれば、自分の信念に忠実でありながら、新しいアイデアや経験を探求することができます。
好奇心はランタンであり、新しい道や可能性を照らします。
誠実さはコンパスであり、道に迷ったり、自分を裏切る方向に進んでしまうのを防ぎます。
インテグリティとは気難しい、厳しいだけの資質ではありません。軸がしっかりしているからこそ、行っていることに意義を感じると共に、それを楽しむことができるのです。
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
ル・カンフは、すべての道はどこかに通じていることを知ることが大切だと述べます。
「正しい」選択を探すのではなく、好奇心を持って進むなら、どんな道も正しいのです。
小さな実験によって、あなたは前進するのです。
何があなたを生き生きさせますか?
私たちは皆、人生を最大限に生きたいと願っています。
しかし、目の前に妖精が現れ、魔法でそれを実現してくれることはありません。
魔法は自分で見つけなければなりません。しかし、一筋縄では見つかりません。
試行錯誤のプロセスです。思考をめぐらし、固定観念を疑い、快適な現状から抜け出すことが必要です。
ビーカーに入れる物質や量、環境の変化によって科学実験の結果が変わるように、かつて発見した方程式も、状況、ものの見方、価値観の変化によって変わる可能性があります。
最後に、以下に列挙する原則は、著者が書籍で紹介したアイデアのいくつかをまとめたものです。
不確実性や不明瞭さを欠陥ではなく機能として捉え、内なる不安や心配を歓迎すべき情報として捉え、過去の栄光よりも今が大事だという生き方をしましょう。20歳でも70歳でも、好奇心が導くままに、どんな方向にも進んでいけます。成功とは、何が自分を最も生き生きとさせてくれるのかを発見する、生涯にわたる実験なのです。
1.ゴールラインを忘れましょう
個人の、そして仕事での成長を求める中で、私たちはゴールを限定し、直線的で狭い道のりに自分を縛り付けてしまいます。今想定しているゴールより幅広い可能性に心を開いてください。
2.自分の脚本を忘れましょう
幼少期からの長い経験に基づいて内面化されたパターンが、私たちの行動を縛っています。その「脚本」に基づいて限定された情熱を追求するのではなく、明白でない道にも関心を寄せるのです。
3.迷いは実験によって晴らしましょう
自信は行動を通して築かれます。迷った時は、個人的な小さな実験をしてみましょう。小さな実験の繰り返しから何かを学ぶことができます。
4.先延ばしと仲良くなりましょう
人はよく先延ばしします。先延ばしは克服すべき敵ではなく、目標(頭)と、感情(心)、スキル(手)が合致していないことを示すシグナルです。なぜ先延ばしするのか好奇心を持って観察し、原因を特定しましょう。
5.不完全さを受け入れましょう
一度に多くのことを成し遂げることはできません。
計画を完全にすることや完璧なタイミングを待つのではなく、その時にできることを優先します。情報が十分でなくても、ひとまずできることをやってみましょう。
6.成長のループを回しましょう
成長したいなら、行動の振り返りが必要です。自分の思考と行動を振り返ることで、自分の思考や感情に気づくだけでなく、それらをコントロールすることができます。
7.混乱を楽しみましょう
人生の歌が突然変わる時があります。慌てたり、戸惑うのではなく、リラックスして耳を傾けましょう。好奇心と機敏さを保てば、混乱は良い変化の源となるでしょう。
8.一緒に探求する仲間を探しましょう
スキルと知識を他の人と共有することで、集団的な好奇心を育みましょう。成功だけでなく、失敗も共有しましょう。他人とつながることで、視野が広がり、影響力が増すだけでなく、セーフティネットが生まれ、変化への適応力も高まります。
9.過去の栄光を手放しましょう
成功体験にいつまでもしがみつくのではなく、今この瞬間に生まれる創造力に目を向けましょう。冒険心を持って、曲がりくねった人生の道を進んでいきましょう。後世に残る自分ではなく、今あなたが生み出せる影響にエネルギーを注ぎましょう。
遊び心を持って好奇心を受け入れれば、小さなトラブルは避けられないが、最終的には大きく成長できる。
~ アンヌ=ロール・ル・クンフThe playful embrace of curiosity inevitably leads to mishaps, but ultimately helps you grow.
~ anne-laure le cunff




