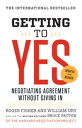交渉の目的は、両者が「Yes」にたどり着くことです。しかし、拙速に「Yes」にたどり着こうとすると、そこにたどり着けなかったり、後で誤解や問題を生んだりします。交渉の初期段階では、相手に「No」と言わせるのです。そうすることで「No」の裏側にある本音を引き出すことができます。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
以前本サイトでは、ネゴシエーション(交渉)に関する名著『Getting to Yes(邦題)ハーバード流交渉術』を紹介しました。
外交や調停など、国際的な交渉の専門家であるウィリアム・ユーリー(William Ury)とロジャー・フィッシャー(Roger Fisher)の共著で、2人はハーバード・ネゴシエーション・プログラム(Harvard Negotiation Project:1979年創立)の共同創始者でもあります。
1981年に出版された本ですが、その分かりやすく的を得た教訓の価値は今でも全く色褪せません。
今回紹介するのは、同じく交渉に関する本であり、2016年に出版された『Never Split the Difference – Negotiating as if Your Life Depended on It(邦題)逆転交渉術 – まずは「ノー」を引き出せ』です。
クリス・ヴォス(Chris Voss, 1957 -)とタール・ラズ(Tahl Raz)の共著ですが、クリス・ヴォスは、典型的なビジネス書作家ではありません。
彼は20年以上にわたりFBIの国際人質交渉官として、生死に関わる緊迫した交渉に幾度も対峙してきました。交渉がうまくいかず、実際に人質の命を奪われたこともあります。
その実経験を基に、ヴォスはテロリストや誘拐犯との交渉で成果をもたらしたのと同じ交渉戦術を、ビジネスの取引や家族間の面倒な言い争い、その他の個人的な交渉まで、誰もが習得できる、日常生活に活かせる実践的なスキルへと昇華させています。
クリス・ヴォスは、この本の中で、自身の交渉術を、交渉術の教科書である『Getting to Yes』と対比させています。また、実際にハーバード・ネゴシエーション・プログラムに受講生として参加した時のエピソードも重ね合わせています。
クリス・ヴォスは、『Getting to Yes』を完全に否定しているわけではありません。実際、その効果と影響を認めています。
しかし、ハーバード大学の交渉モデルは、理論に傾倒していて、現実世界における、理論が通じない相手との交渉や、感情が大きく影響する状況では必ずしも通用しないと主張します。この点で、本書は、大胆で物議を醸しながら、現実の交渉における実務上の核心を突いています。
今回は、『Getting to Yes』と対比しながら、彼の交渉術を紹介していきます。なお、いつものように私は英語版しか読んでいませんので、日本語版との表現等の違いについてはご了承下さい。
~ ~ ~ ~ ~
本意に基づいた交渉(Principled negotiation)
本書の説明に入る前に、以前紹介した『Getting to Yes』のポイントを簡単におさらいしましょう。
『Getting to Yes』の核となる考え方は、交渉においては、お互いの主張や勝ち負けではなく、その主張の背景にあるお互いが本当に望むものは何なのかを突き止め、双方に真の利益をもたらす合理的な解決策を見つける交渉を行うことでした。
これを「本意に基づいた交渉(Principled negotiation)」と言います。
交渉におけるよくある間違いは、お互いの主張を戦わせ合い、ポジション争いをしてしまうことです。
実際に多くの交渉事が「お互いの主張=ポジション」をめぐる攻防になります。
「ポジション」とは自分が望むものを相手に提示するために言葉に仕立てたものです。私たちは自分たちが望むものを考えて明らかにし、それを相手に伝えるために文章や態度に落とし込みます。それがポジションです。
ポジション争いの問題は、双方の目的が「相手に勝つこと」になってしまいがちなことです。
しかし、本当に私たちがたどり着きたいゴールは相手に勝つことではないはずです。ゴールは自分の利益になること、さらにはお互いに利益となる結論を導くことです。
双方のポジションに注意が向けば向くほど、双方が根本的に望んでいることには注意が払われなくなり、お互いが本当に望む合意にたどり着く可能性は低くなります。たどり着いた結果は、実はお互いの本来の思いとは離れた、別のところであることも珍しくないのです。
相手の主張する直接的な内容にとらわれ過ぎず、それに正面から反論するのではなく、お互いの主張の背景にある意図や動機を知るのです。双方が真に望むものがいったい何なのか、理解することにフォーカスするのです。両者が本当に望む本意(Principle)を明らかにし、お互いの真の利益(Interest)を追求するのです。
それを理解することができれば、交渉そのもののに対する姿勢とプロセスが劇的に変わるでしょう。
~ ~ ~ ~ ~
戦術的共感(Tactical empathy)
では次に、ヴォスが『Getting to Yes』のアプローチがなぜ不十分だと述べているのか、以下に詳しく説明していきましょう。
ヴォスは、交渉とは論理や妥協ではなく、相手の感情を理解することだと説きます。
彼は誘拐犯やテロリストなどとの交渉を数多く経験してきました。そのような交渉では、一般的なビジネスの交渉とは異なり、相手が理性的で、理論的な交渉プロセスを理解しているという前提を持つことは非現実的です。
むしろ、交渉相手は、一瞬の油断もできないという極度の緊張下にあったり、大きなストレスを抱えています。そのため、興奮して理性を失ったり、強い感情から衝動的な行動を取ることもあります。
また、誘拐犯やテロリストは、社会への不満や、世の中から受け入れられていない苛立ちを抱えていることもあります。そのような人たちは、何よりも、自分の話を聞いてもらいたいと思っています。自分を理解してもらいたい、考え方を受け入れてもらいたいと思っています。
そのため、相手がどんなに残虐な犯罪者であろうが、まずは交渉相手に共感し、相手の話を聞くことが大切です。相手と心を通わせることができなければ、その先に進むことができないからです。
これを「戦術的共感(Tactical empathy)」と呼びます。つまり、戦略的に相手に共感するのです。理解していることが相手に伝わることで、信じられないほどの影響力を発揮できるようになります。
相手に「イエス」と言わせるには、論理的に相手を納得させることが前提になる。しかし、交渉は論理ではなく感情だ。感情の流れをコントロールできれば、結果をコントロールできる。
~ クリス・ヴォス
“Getting to Yes assumes you can reason with people into agreement. But negotiation isn’t about logic — it’s about emotions. Once you control the emotional flow, you control the outcome.”
~ Chris Voss
~ ~ ~ ~ ~
本意に基づいた交渉と、戦術的共感の違い
人間は理性的な動物であると同時に、感情的な動物です。
『Getting to Yes』の「本意に基づいた交渉」は、お互いがある程度の理性を維持していることが前提になっています。
これに対して、「戦術的共感」は、人間の感情に対応する交渉術です。理論的な話し合いの効果が限定的な場面で、感情的な相手といかに交渉するかという違いがあります。
ヴォスは、犯罪者のみならず、人間の意思決定は合理的ではない場合が多く、双方に利益のある解決策に歩み寄っていくことを重視する交渉モデルよりも、感情に影響されるケースの方が多いと主張します。
実は、国と国の交渉、誘拐犯やテロリストとの緊迫したハイリスクな対峙の場のみならず、理性が通じない、あるいは感情に支配された交渉の場は私たちも日常的に経験しています。
今までの経験を振り返ってみて下さい。個人的な交渉の場で、相手が感情的になって建設的な議論ができなかったり、逆に自分の方がついカッとなって声を張り上げてしまったことはないでしょうか?
本書は交渉に対する根本的に異なる視点を提示しています。それは、論理や妥協ではなく、感情論や心理学に基づいたものです。
この点で優れた交渉とは、勝つことではなく、相手を理解することなのです。特にストレス下において、相手の感情を理解し、こちらに悪意がないことを認識してもらうことで、行動に影響を与えるのです。
次の表は、『Getting to Yes』と本書の交渉術の違いを示したものです。
| Getting to Yes ハーバード流交渉術 | Never Split the Difference 逆転交渉術 |
|
|---|---|---|
| 原則 | 「本意に基づいた交渉」 両者に利益のある公平な合意にたどり着こうとする | 「戦術的共感」 相手の感情を理解し、その気持ちを表現することで緊張をやわらげ、信頼と影響力を築く |
| 特徴 | 理性的。ポジションに捉われず、双方に合理的な結論を導く | 心理的。相手が何を求めているのか、どう感じているのかを明らかにする |
| 人 | 人を問題から切り離す | 人こそが問題 |
| 前提 | 人間は合理的 | 人間は感情的 |
| 相手 | 合理的な問題解決者 | 感情に左右される意思決定者 |
| アプローチ | お互いの主張の背景にある本当の意図や動機に焦点を当てる | 安全性優先。相手に安心感を与えて話させて、主導権を握っていると感じさせる |
| 目標 | WIN-WIN、相互利益 | Win-Winは必ずしも現実的ではない |
| トーン | 理論的、客観的、公平性 | 感情的、安全性、影響力 |
| プロセス | 決まった手順に従う | 合理性を前提にしない、予測困難 |
| 交渉例 | 長期的なパートナーシップ、契約交渉 | 人質解放、緊急性が高い、感情が支配する交渉 |
~ ~ ~ ~ ~
Getting to No 「ノー」がコントロールを生み出す
ロジャー・フィッシャーとウィリアム・ユーリーによる『Getting to Yes』が、双方が「イエス」へと向かう協力的な環境を作り出すことを重要視しているのとは対照的に、クリス・ヴォスは「ノー」の重要性を強く主張しています。
「双方をイエスに導くこと」、これは理にはかなっていますが、実際の人間関係において、常に「イエス」を求めることは、むしろ、相手にプレッシャーを与えたり、操られていると感じさせ、本心を知ることを妨げることがあります。
ヴォスは、特に初期段階では相手に「イエス」と言わせるべきではないと言います。相手に拙速に「イエス」と言わようとすると、相手はプレッシャーを感じます。追い詰められていると感じ、口を閉ざすようになります。
交渉過程で相手から「ノー」を引き出すことで、真のコミュニケーションを促し、相手の本当のメッセージを引き出すことができます。クリス・ヴォスは、「イエス」は交渉の最終到達地点ではあるが、「ノー」が交渉の始まりになると言います。「イエス」にたどり着くには、「ノー」から始まる、双方が理解し合う環境づくりが必要なのです。
相手が「イエス」を繰り返すとき、会話の主導権はこちら側にあります。
しかし、こちらが主導権を握っている限り、相手から本心を聞くことはできません。相手が「イエス」と答える時、相手はただこちらに合わせて、相槌を打っているだけ、あるいは時間を稼ごうとしているだけです。
しかし、相手が「ノー」と答える時、会話の主導権は相手に移ります。この主導権を握っているという感覚が、率直な対話への扉を開きます。なぜ「ノー」なのか、その理由を引き出すことができます。
交渉の初期段階では相手に「ノー」と言わせるのです。
そのことで、何かを押し付けられるのではないかという感覚が消え、相手は安心だと感じ、交渉を自分がコントロールしている感覚を得ることができます。相手が安全だと感じることで初めて、相手から本音を引き出すことができます。相手はなぜノーと言ったのかを説明し始め、真の懸念や関心を明らかにし始めます。真実が明らかになることで、解決へのヒントを得ることができるのです。
具体例を挙げましょう。
例えば、あなたが取引の交渉の場で「このパッケージは良いアイデアだと思いませんか?」と相手に言ったとします。
相手は「はい、そうですね」と返事をします。しかし、これは実際には丁寧な「いいえ」で、本心は分かりません。会話もそれ以上発展しません。もし発展したとしても、その場の体裁を整えるだけの意見が返ってくるだけです。
クリス・ヴォス流のアプローチでは「このパッケージをさらに追及しようと思っていますが、間違っているでしょうか?」と聞くべきです。
これで「いいえ」という返答を誘うことができます。相手が「いいえ、おかしなことではありません」と返答すれば、実際に交渉に参加したことになります。この小さな「いいえ」は、相手に会話の主導権を与え、さらに「この点で改善できる余地があると思います」など、相手の本音を引き出すことができるのです。
別の例として金額交渉を挙げましょう。
「95,000ドルで合意できますか?」と尋ねる代わりに、「95,000ドルで検討するのは難しいでしょうか?」と聞くのです。相手が「いいえ、無理ではありませんよ」と答えた場合、さらにその理由や条件を引き出すことができ、心理的に同意へ前進することができます。
さらに別の例として仕事を想定してみましょう。
リーダーであるあなたは、メンバーに対して「この新しいプロジェクトの担当をお願いしますね」と言うかもしれません。メンバーは「イエス」としぶしぶ同意するかもしれませんが、後になって不満や問題が噴き出すかもしれません。
代わりに、「今、あなたにこのプロジェクトを割り当てるのは良くないですか?」と聞くのです。
「いいえ、大丈夫です」と答えられた場合、それは真のコミットメントです。「はい、それは良くない考えです」という答えが返ってきた場合でさえ、あなたは率直な意見を引き出すことができたため、どうすれば解決できるか一緒に話し合うことができるのです。
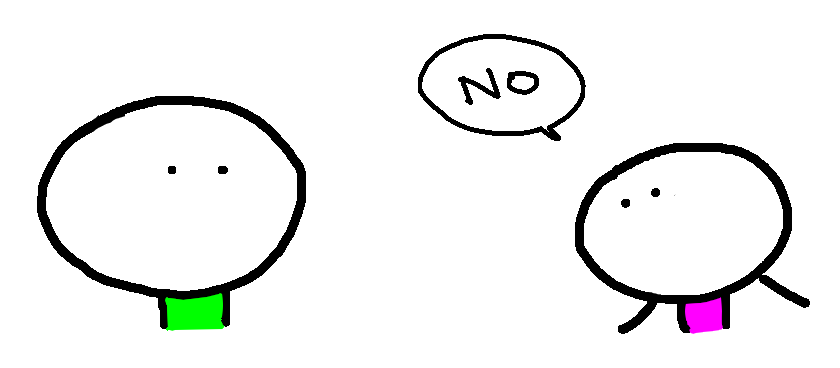
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
クリス・ヴォスのアプローチは心理学や行動経済学を応用しています。
交渉相手に対峙するにあたって、エンパシー(共感)やエモーショナル・インテリジェンスを利用して、危険な相手とでさえ、交渉の場の心理的安全性を確保しようとしているのです。相手に「ノー」と言わせることは、相手に安全感とコントロール感を与え、相手の防御の障壁を下げることができます。
「イエス」を強要すると、懐疑心や不安を引き起こします。むしろ相手の本心が読めなくなります。人は安全だと感じてはじめて、相手の話を聞き、問題解決に積極的に取り組むようになります。
「ノー」は真のメッセージを引き出すのに役立ちます。なぜなら、次のような効果があるからです。
- 隠れた動機を明らかにする ~「何が彼らを本当に阻んでいるのか?」
- 誤解を解く ~「なるほど、問題は価格ではなくタイミングだったんですね。」
- 信頼を築く ~ 「私がノーと言えることを相手は尊重してくれている。」
真の交渉とは、手っ取り早く「イエス」を追い求めることではないことではありません。相手が安心して「ノー」と言えるようにすることが重要です。その一言で扉が開き、誠実で生産的な会話が生まれるのです。
書籍の中では、ミラーリングやラベリングなどのその他の心理的ツールや、効果的な質問の仕方などの対話ツールも紹介しています。興味がありましたら、ぜひお手に取ってみてください。