習慣や誤った思い込みに基づく無意識の行動が、私たちの世界観を形作っています。人は必ずしも合理的に情報を処理するのではなく、過去の経験や物事の提示のされ方によって心理的な影響を受けます。コントロールできないことも、コントロールできると錯覚するのです。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
みなさんにはこのような経験はありませんか?
- 大学受験や採用面接の日は「ラッキーシャツ」を着たり「勝負パンツ」を履く
- 大事なスポーツの試合では、競技場に必ず右足から入る
- エレベーターで早く扉が閉まったり、歩行者用横断歩道で信号がはやく青に変わるように、何度もボタンを押す
- サイコロを振る時、高い目を出したいときは強く、低い目を出したいときは弱く振る
すこし考えれば、このような行動が、自分の望む結果につながるものではないことが分かります。
しかし、私たちはこれとさほど変わらないことを日常的に繰り返しています。
~ ~ ~ ~ ~
コントロールの錯覚 The Illusion of Control
今回紹介するエレン・ランガー(Ellen Langer, 1947 -)は、アメリカの社会心理学者であり、マインドフルネス、意思決定、コントロールの知覚、健康心理学を専門とした研究者です。彼女はハーバード大学で終身在職権を得た最初の女性の心理学教授でもあります。
彼女が1975年、専門誌に「コントロールの錯覚(The Illusion of Control)」(1) を発表した当時、米国の心理学は行動主義(behaviorism)と確率的意思決定モデル(probabilistic models of decision-making)に支配されていました。
ランガーは、彼女のキャリアを通して、習慣や誤った思い込みに基づく無意識の行動が、私たちの世界観をいかに形作っているかを研究し、人間は必ずしも合理的に情報を処理するのではなく、文脈や社会的手がかりによって心理的な影響を受けることを示し、当時主流だったそれらの考え方に異議を唱えました。
人は、明らかに自分が結果に影響を及ぼすことができないような状況でも、あたかも結果をコントロールできるかのように振舞うことがあります。また、望んだ結果が起きると、実際は何が起きるか自分では影響を及ぼせない場合でも、それをコントロールしていたのは自分だと信じる傾向があります。
彼女が論文で発表したコントロールの錯覚(コントロールの幻想)とは、「物事をコントロールする自分の能力を過大評価すること」や「コントロールできないことに対して、コントロールできると錯覚して行動すること」です。
日本には「運も実力のうち」という言葉があります。
その言葉が示す通り、「運」と「実力」との間に何らかの関係が存在することを信じる人は多いかもしれません。しかし、両者がどのくらい結びついているかを説明することはできません。
実力やスキルが必要とされる課題では、行動と結果の間に因果関係があり、結果をコントロールすることができます。一方で、運による出来事の結果は偶然です。成功するかどうかは制御不能です。
ランガーは論文で、人は、偶然の出来事にあたかも何らかの影響を及ぼすことができるかのように行動することを示す、600人以上の参加者を対象とした6つの実験を報告しています。それは次のような実験です。
実験1
参加者は、高い数字を引いた方が勝つカードゲームを行いました。対戦相手は、自信があり有能な相手と、緊張し不安な相手のいずれかでした。実験の結果、ゲームの勝敗は完全にランダムであるにもかかわらず、参加者は、弱そうに見える相手と対戦した時の方が、勝利に自信を高めたことが分かりました。
これは、「実力」の論理を、ランダムな事象にまで広げて当てはめたコントロールの錯覚の一例です。
実験2
参加者は、自分で宝くじを選ぶか、自動的に割り当てられたくじを受け取るか、どちらかを選びました。当選確率は同じですが、自分でくじを選んだ人の方が、手に入れたくじを高く評価し、購入後交換してもよいと言われても、交換したがらないことが分かりました。
これは、「自分が選択する」ことによって、ランダムな結果をコントロールできると感じた、コントロールの錯覚例です。
実験3
参加者は、馴染みのあるくじか、あまり見たことのないくじのどちらを引くかを選びました。馴染みのあるくじを引いた人の方が、そのくじの価値をより高く評価し、当選確率が高いと考えました。
「馴染みがある」ことで、結果をよりコントロールできると感じたのです。
実験4
このカードゲームの実験では、自分でカードをめくる参加者もいれば、代理人にめくらせる参加者もいました。また、事前にゲームの予行練習をした参加者もいれば、しなかった参加者もいました。結果は、自分でカードをめくった参加者と、練習を行った参加者は、より勝つ可能性が高いと感じました。
つまり、能動的、主体的な関与によって、受動的に関わるよりもランダムな事象をよりコントロールできると思ったのです。
実験5
実験5は競馬です。競馬場で、馬券を買う前後に、自分が選ぶ馬が勝つことにどのくらい自信があるか質問をしました。その結果、馬券を購入した後の方が、購入前よりも自信が高まることが分かりました。
人は何かにコミットすると、その可能性が高まると錯覚するのです。
実験6
最後も宝くじです。参加者は2つの異なる方法で宝くじを受け取りました。
1つのグループは一度にすべての数字を受け取りました。もう1つのグループは3日間、1日1つの数字を受け取りました。結果、2番目のグループの方が、自分の宝くじの当選確率に対する自信が高まったのです。
人は、長い時間出来事に関わることによって、たとえその結果が偶然によるものであっても、よりコントロールできると感じるようになるのです。
~ ~ ~ ~ ~
コントロールの錯覚は悪いことなのか?
ランガーの研究は、不確実な状況での人の考え方を知るのに役立ちます。人が確率を誤って評価するのは、統計を知らないからではありません。認知の仕組みや文脈によって、課題の性質(実力 vs. 運)を誤って解釈するためです。
つまり、コントロール不能な課題に、選択、馴染みやすさ、直接的関与などのコントロール可能な手がかりが結び付けられると、人は、誤って「スキル思考」を適用してしまい、運に左右される出来事を、あたかもコントロールできるかのように扱ってしまうのです。
では、なぜ人は偶然の出来事を自分のコントロール下にあるかのように行動する必要があるのでしょうか?
そして、これらの錯覚は悪いことなのでしょうか?
実は、そうとも限りません。
コントロールの錯覚は、単純にネガティブなものともポジティブなものとも言い切れない、心理的な諸刃の剣です。そのメリットとデメリットの両方を紐解き、バランスを取る方法を考えてみましょう。
~ ~ ~ ~ ~
健全なコントロールの錯覚:錯覚のポジティブな側面(メリット)
コントロールの錯覚は、特に感情面とモチベーションの面で私たちを助けてくれます。その例を紹介しましょう。
1.自信とモチベーションを高める
自分がコントロールできると信じることで、私たちは前に進むことができます。
例えば、努力すれば成功できると強く信じる起業家は、たとえそれに偶然の要素が絡んでいるとしても、成功するまで粘り強く努力し続けることができます。
この感覚は、主体性、レジリエンス、そして達成感を得るために不可欠です。
2.不確実な状況における不安を軽減できる
コントロールの感覚を持つことで、プレッシャー下でも冷静さを保つことができます。
例えば、病気と闘う患者は、たとえ完治が約束されていなくても、その可能性があると信じれば、希望を保つことができます。また、未知の領域に事業を展開するような仕事でも、コントロールの感覚があれば、冷静に業務を進めることができます。
3.努力と責任感を促す
自分の行動次第だと考える人は、運を天に任せて何もしないのではなく、できるだけのことはしようと努力したり、責任感を強く持つ傾向があります。
4.幸福感をもたらす
適度なコントロールの錯覚は、楽観主義と自尊心を高めます。自分が世界に影響を与えることができると信じる人は、より充実感を感じ、無力感を感じにくくなります。
~ ~ ~ ~ ~
不健全なコントロールの錯覚:錯覚のネガティブな側面(デメリット)
しかし、錯覚が強すぎたり、現実から乖離しすぎると、誤った判断や現実逃避につながる可能性があります。
1.過信とリスクテイク
自分のコントロール感を過大評価すると、リスクや警告のサインを無視してしまいます。ギャンブルで負け続けていても、絶対に巻き返せると信じれば、賭け続けるかもしれません。
何回失敗しても次こそは成功できると信じ続けることは、偶然が支配する局面ではデメリットになります。
2.現実の否定
コントロールできないものをコントロールできると信じることは、生産性のない思考やメンタルの問題につながることがあります。例えば、ある人は、交際相手との関係を修復できると信じて、有害な関係を持ち続けるかもしれません。
3.コントロールできない結果を自分のせいにする
自分のコントロール感を強く持つ人は、物事がうまくいかないと、たとえそれがコントロール不能なことであっても、自分のせいだと感じてしまい、不必要な罪悪感や羞恥心を持つことがあります。
例えば、子どもが、自分の力ではコントロールできない親からの理不尽な要求を満たせず、自分を責めることなどがあります。
4.マイクロマネジメントとストレス
成功や失敗には、運が関わっています。完全にはコントロールできないのに、必要以上の時間と労力をかけたり、細部までコントロールしようとして、前に進めないだけでなく、それを他人に押し付けて、他人に必要のないプレッシャーをかけてしまうことがあります。
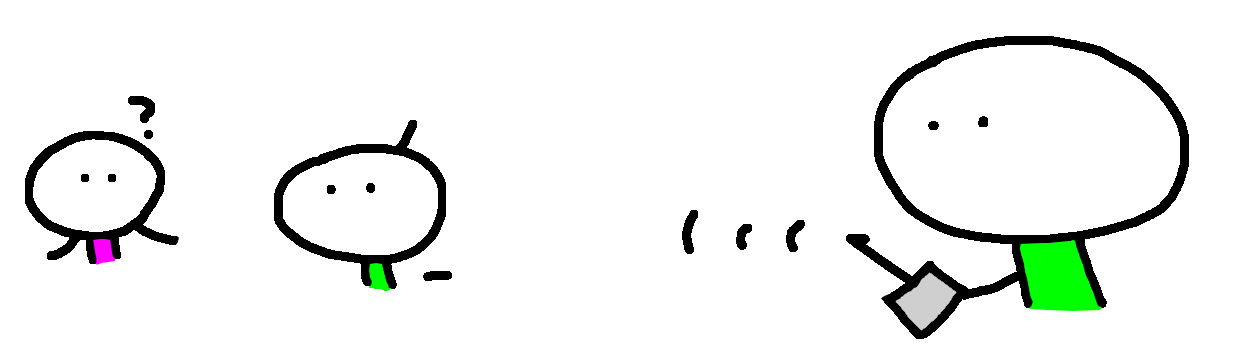
~ ~ ~ ~ ~
バランスを取る
以上説明したように、「健全なコントロールの錯覚」には、現実的な楽観主義、影響を与えられるものへの集中、柔軟な思考、モチベーションの維持、感情の安定などが含まれます。
一方で、「不健全なコントロール錯覚」には、自信過剰、硬直した考え方、フラストレーション、誤った決断などが含まれます。
適度なコントロールの錯覚は、私たちに力を与えてくれます。
過度のコントロールの錯覚は、私たちを惑わせてしまいます。
重要なのは、その違いを知ることです。
では次にどのようにしてそのバランスを取ることができるのか見ていきましょう。
1.「影響」と「コントロール」を区別する
私たちは、努力、準備、態度を変えたりして、周囲の人たちに影響を与えることはできます。しかし、すべての結果をコントロールすることはできません。その事実を認めるのです。
2.結果を振り返る
結果が出た後、じっくりと振り返ってみましょう。
「コントロールできたのは何だったのか? 運や他の要素によるものは何だったのか?」
こうすることで、現実的な認識を育むことができます。
3.楽観主義を戦略的に活用する
自信は、現実面でのリスクを見失わない限り、有用です。楽観主義を意図的にうまく利用しましょう。
4.不確実性を受け入れる
逆説的ですが、コントロールできないことを受け入れることは、私たちを弱くするのではなく、穏やかかつ賢くします。
5.適応力を保つ
適度な自信と柔軟性は、過信と硬直性に勝ります。現実が変化したときに進路を修正できることで、コントロールの幻想を健全なレベルに保つことができます。
コントロールできていると感じることは、たとえ実際にはそうでなくても、私たちの思考、意思決定、そして生き方を大きく左右します。
それは心理的な罠であると同時に、人間の強さの源でもあります。過度の幻想は誤りにつながりますが、小さな希望に満ちた幻想は、努力、粘り強さ、そして変革を駆り立てる力となるのです。
~ ~ ~ ~ ~
コントロールの錯覚から、マインドレス、マインドフルへ
コントロールの錯覚を論文で発表したエレン・ランガーは、実は「マインドフルネスの母」とも言われるほど、心と体(mind and body)の研究で有名です。
ここで、ランガーが1970年代初期に研究したコントロールの錯覚の概念が、その後、1980年代以降のより包括的なマインドフルネス理論へとどのように発展したかを辿ってみましょう。
なお、ランガーが意味するマインドフルネスとは、スピリチュアルや仏教から派生して使われる、いわゆるマインドフルとは異なります。
彼女が使うマインドフルネスは「好奇心や柔軟性を保ちながら状況を認識し、さまざまな視点にオープンで、自分の前提に疑問を持ち、新しいことに気づくことができる」という、積極的、能動的に「意識している」状態、意識的な認知と思考です。
心を空っぽにしたり、思考を停止した「自動操縦」で行動するのではなく、意識的に状況を把握し、より明確かつ柔軟に考えることです。
繰り返しますが、コントロールの錯覚は「人はしばしば、以前習得したスキルやパターンを、それが当てはまらない状況(偶然の出来事)にでさえ、ほとんど無意識に適用してしまう」ということでした。
ランガーは「錯覚」は単にコントロールに関することだけではなく、認知が硬直していて、状況の違いに気づかない「マインドレスネス」の状態でもあり、コントロールの錯覚は、より広範な現象の1つに過ぎないことに気づきます。
実は、人は人生の大半を「自動操縦」で生きているのです。コントロールの錯覚が時々起きるのではなく、世界との関わり方そのものがほとんどマインドレスなのです。
ランガー自身の著書『Mindfulness(邦訳)マインドフルネス』(1989年)の中で、彼女はこの2つを明確に結び付けています。
私たちが錯覚と呼ぶものの多くは、マインドレスネス、つまり過去に作られたカテゴリーや区別に頼ることから生じている。マインドフルネスとは、新しいことに気づき、錯覚が定着するのを防ぐプロセスである。
~ エレン・ランガー
Much of what we call illusion results from mindlessness — from relying on categories and distinctions made in the past. Mindfulness is the process of noticing new things, thereby preventing these illusions from taking hold.
~ Ellen Langer
私たちは目新しいものの考え方や文脈の変化に気がつきにくいのです。
ものの見方や、解釈の枠組みが固定されてしまっているからです。
今までのやり方や考え方やルールやカテゴリーを深く考えずに当てはめて、何度も同じ間違いを繰り返して、根本的な原因にたどり着かず、フラストレーションを抱えているのです。
これを踏まえ、ランガーの後期の研究では、コントロールではなく、「意識」という観点から錯覚を再構築し、マインドフルネスを次のように定義しました。
マインドフルネス
- 新しいものの見方や考え方に積極的に気づく認知プロセス
- 文脈の変化への敏感さ
- 多様な視点にオープンであること
- 不確実さを認識すること
- 自分がどう解釈しているかに気づくこと
- 自分の考え方の枠組みや期待を固定しないこと
マインドフルであることは、錯覚に気が付いていること、固定観念から脱却できることであり、私たちに柔軟性、創造性、そして幸福感をもたらします。
逆に、マインドレスは、現実への見方が硬直化していて、古い考え方やルールから抜け出せず、新しいものの見方や新しい発想に気づかないことです。ランガーのマインドフルネス理論は、錯覚はマインドレスネス、つまり古い認知の枠組みを吟味せずに適用してしまうことの症状だとしています。
私たちは、錯覚を完全に排除するのではなく、マインドフルを通して、錯覚が脳の構築物であることに気づき、それを定着するのを防ぎ、悪い罠にはまらないようにしつつ、良い点は利用するのです。自分自身の認知構造への気づきは、錯覚を防ぎ、柔軟性、健康、そして真の関与を促進します。
下のYoutubeで、ランガー自身がコントロールの錯覚や、マインドレスネス、マインドフルネスについて説明しています。ご興味がありましたら、ご覧ください。
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
エレン・ランガーの研究は、心理学をはじめ、様々な分野に大きな影響を与えました。
認知心理学と社会心理学の分野では、認知バイアス、ヒューリスティックス、そして自信過剰に関する研究のきっかけとなり、行動経済学の大家であるダニエル・カーネマンやエイモス・トベルスキーといった研究者によってさらに発展しました。
以前紹介した、アルバート・バンデューラの自己効力感などに関する研究にも影響を与えています。
バンデューラは、1989年「真実に基づく判断は自己制限的になり得るが、自分の能力に関する楽観的な自己評価は、それが過度にかけ離れていない限り、有利になり得る」と書いています。(2)(4)
また、1997年には「誤差の範囲が狭く、失敗が大きな代償や損害をもたらす可能性のある活動においては、正確な効力感の評価が、個人の幸福を実現する」とも書いています。(3)(4)
組織心理学や経営心理学の分野においては、経営者や投資家が、複雑な市場や組織の成果に対するコントロールを過大評価しているという考えは、ランガーの理論に直接由来します。彼女の研究は、マイクロマネジメント、過剰な計画、そして過信がビジネスリーダーに根強く残る理由を説明しています。
最後に、エレン・ランガー自身の有名な研究に1979年に行われた「反時計回り実験(Counterclockwise Study)」があります。
これは、高齢の男性たちを20年前の生活環境を再現した施設に1週間滞在させ、「あたかも今が1959年であるかのように振る舞う」ように指示した実験で、参加者は、20年前の自分として生活し、当時の出来事や音楽、映画などについて語り合いました。結果として、参加者たちは、記憶力の向上、柔軟性の改善、実際に外見的に若く見えるなど、身体的・認知的な若返り効果を示しました。
これは、コントロール、年齢、健康に関する信念が、生物学的および心理学的結果に影響を与える可能性があることを示唆しています。
このように、コントロール錯覚は、知覚がどのように現実を形作るかという、より広範なテーマへと発展したのです。
~ ~ ~ ~ ~
参考文献
(1) Ellen J. Langer, “The Illusion of Control”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 32, No. 2, 311-328, 1975.
(2) Albert Bandura A, “Human agency in social cognitive theory“, The American Psychologist, 44 (9): 1175–1184, 1989/9.
(3) Albert Bandura A, “Self-efficacy: The exercise of control“, New York: W.H. Freeman and Company, 1997
(4) “Illusion of control“, Wikipedia




