イギリス人は疑い深く、控えめで、独特のユーモアと皮肉があります。アメリカ人は実践的、直接的で、楽観的、行動志向です。そんなアメリカ人は、イギリス人の真意がわかりにくいと感じ、一方のイギリス人も、アメリカ人は直接的すぎて繊細さに欠けると感じます。その違いの背景にあるイギリスの経験主義とアメリカの実用主義を紹介します。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
以前本サイトで、経験主義(Empiricism)をベースとするイギリスやアメリカと、理性主義(Rationalism)をベースとする大陸ヨーロッパ諸国との思想の違いについて書きました。
大陸ヨーロッパが理性主義(Rationalism)と結びついているのと対照的に、アメリカとイギリスは、歴史的に経験主義と強い結びつきを持っています。
経験主義とは、経験があらゆる知識の基盤となるという信念です。経験主義によれば、人は白紙の状態で生まれ、知識は経験から事後的に蓄積されていきます。
では、アメリカとイギリスは同じように経験主義に結びついているのかと言うとそうではありません。アメリカとイギリスでは、経験主義の捉え方に大きな違いがあります。
例えば、何か悪いことが起きたとき、アメリカ人は「残念だ That’s too bad」とか「それはひどい That’s terrible!」、「お気の毒に I’m sorry to hear that」などと言いますが、イギリス人は「もっと悪かったかも It could be worse」とか「少なくても○○はよかった At least, ○○ was good」などと言うかもしれません。
逆に、何か良いことが起きたとき、アメリカ人は「それはすごい! That is awesome!」「すごくいいね I love it!」などと言いますが、イギリス人は「そんなに悪くないね That is not so bad」などと言うかもしれません。
そんなアメリカ人は、こんなイギリス人を、真意がわかりにくいとか、失礼だと感じることがあります。一方で、イギリス人の方も、アメリカ人は真面目すぎるとか、直接すぎて繊細さに欠けると感じています。
今回は、アメリカとイギリスのこれらの違いの背景にあるのは何なのか、アメリカとイギリスの共通しながらも異なる考え方について、主に経験主義の視点から見ていきます。
~ ~ ~ ~ ~
イギリスの古典的経験主義
ジョン・ロック(John Locke, 1632 – 1704)、ジョージ・バークリー(George Berkeley, 1685 – 1753)、デイヴィッド・ヒューム(David Hume, 1711 – 1776)といった哲学者から始まったイギリスの経験主義では、人間の知識形成において、経験や感覚が大きな役割を果たすと考えます。先ほど書いたように、経験から知識を得るという考え方です。
イギリス人は抽象的な理論よりも慣習的な経験を重視します。伝統と前例を重視し、 規範は原則ではなく習慣から生まれます。知識は、経験に基づいて明らかになったことを少しずつ積み重ねることで形成され、新たな証拠によって修正されていきます。
イギリス人の疑い深さ、慎重さ、控えめな態度
アメリカ人に比べると、イギリス人の方が疑い深く、慎重で、控えめなイメージがありますね。それはこのイギリスの経験主義が影響しているからです。
なぜ経験主義と疑い深さや慎重さが結びつくのか、ピンと来ないかもしれませんので、もう少し詳しく説明しましょう。
イギリス的な経験主義の核にあるのは、すべての知識は経験、特に感覚的経験(見る、聞く、触るなど)から得られるという考えです。逆に言うと、観察によって検証したり、実際の体験によって確かめない限り、物事を信用できません。
少し乱暴な言い方をすると「世界を観察することで学ぶ」ため「自分の目で確かめるまでは信じない」のです。
自己は経験によって形成されます。他人はあなたの行動を観察しない限り、あなたを真に「知る」ことはできません。そして、たとえ観察できたとしても、部分的にしか知り得ません。すべてを知り尽くすことはできません。
そこには、抽象的な理論への懐疑心があります。
確実とされるものを疑う姿勢、主張における注意深さや謙虚さ、そして何かを決めつけることや断言することへの社会的な抑制があります。経験に基づいていない何かを主張することはよく思われません。
イギリス人は「その考えは間違っている」と言う代わりに「それは興味深い視点ですね」と言うかもしれませんが、それは、不確実性を尊重し、確信できないことを断言することをためらう姿勢を反映しています。
これが、経験主義が懐疑主義につながる理由であり、イギリス人が疑い深く慎重で、直接的な表現よりも間接的な表現を好む理由の1つです。
イギリス人の曖昧さ、皮肉、独特のユーモア
また、典型的なイギリス人の特徴に曖昧さ、皮肉、独特のユーモアがありますね。他の国の人たちにはなかなか理解できないものもあります。これらも、少なくとも部分的には、イギリス的な経験主義と結びついています。
皮肉とは、あることを言いながら別のことを意味することです。物事を額面通りに受け取らず、曖昧さや別の解釈の余地を残します。つまり、あることを言いながらも、それに完全にコミットすることを避けるのに最適なツールです。
皮肉、控えめな表現、自虐的な表現を使い、イギリス人は時々、言いたいことの反対のことをさりげなく言います。例えば、大惨事の後で「まあ、うまくいったね」と言ったりします。
要するに、物事を真に受けたり、断言したり、率直に話しすぎない、ということです。
経験主義を重視する文化では、自分の信念にあまりに真剣になりすぎると、独断的な印象を与えてしまう危険性があります。皮肉は主張を和らげ、「私はすべて知っているわけではないことを分かっていますよ」というシグナルを送ります。絶対主義を回避し、曖昧さを伝える方法なのです。
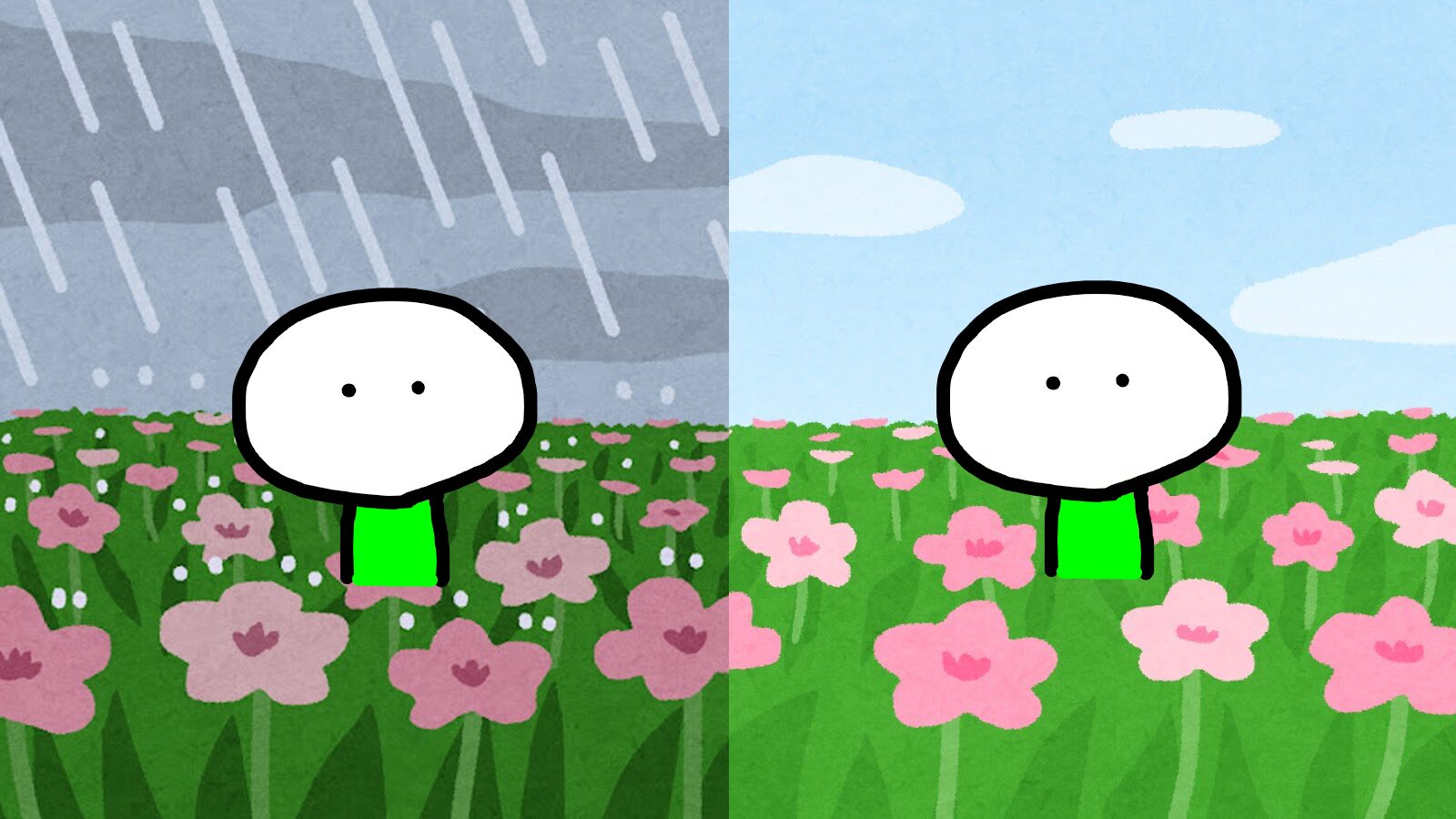
~ ~ ~ ~ ~
アメリカの実用的経験主義
一方で、アメリカの思想家は、イギリスの古典的経験主義をアメリカ独自の哲学である実用的な経験主義、プラグマティズム(実用主義、Pragmatism)へと変容させました。
その起源は1870年代、チャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce, 1839-1914)、ウィリアム・ジェームズ(1842-1910)、ジョン・デューイ(John Dewey, 1859-1952)などのアメリカの哲学者にあります。
実用主義の核にあるのは、信念とは実際に機能するもの、知識とは問題解決のための道具であり、有用な結果をもたらすものだという考えです。
つまり、真実は「機能するもの」「うまくいくもの」です。真実は発見されるものではなく、作られるものです。アイデアは問題を解決するための道具です。
1878年、実用主義(プラグマティズム)の父とも言われるパースは、これを次のように表現しました。
概念化しようとする対象の実際的な効用を考えなさい。その効果に対する概念が、対象についての概念のすべてなのだ。
~ チャールズ・サンダース・パース
Consider the practical effects of the objects of your conception. Then, your conception of those effects is the whole of your conception of the object.
~ Charles Sanders Peirce
楽観的、実践的、行動志向、解決志向
アメリカのプラグマティズムは、楽観的、直接的で、行動志向、解決志向です。
実験的、実践的で、新しいアプローチを試す傾向があります。
良い結果を得るために、変化することに対してオープンです。
前例よりも有用性に重きを置き、自己改善、進歩を支持します。知識は、論理や歴史的な根拠ではなく、それがもたらす効果によって判断されます。
「なぜうまくいくのか」を分析するよりも「うまくいくならやってみる」が重要です。
真実は進化します。固定されたものではなく、世界を切り開くのに役立つのならば、それが「真実」になります。
アイデアを共有することで、共に真実を築くことができるため、オープンな姿勢、友好的な行動が尊重されます。人と協業することで、問題を解決し、物事を前進させることができます。知識は社会的なものであり、コミュニケーション、協力を通じて生み出されます。
より直接的な表現
ユーモアに関して言えば、アメリカ人のユーモアはイギリス人より直接的で、文字通りに表現されます。ユーモアに限らず、すべてがより直接的です。
例えば、アメリカ人は「これは今までで最高のコーヒーだよ! This is the best coffee ever!」とか「彼は最高だよ He’s a really nice guy」などと言うかもしれませんが、イギリス人はそのような言い方はしません。
イギリスで「彼は最高の人物だよ!」なんて言おうものなら、むしろ怪しまれるかもしれません。イギリスでは、「彼は大丈夫そうに見えるね He seems alright」とか「悪い奴じゃないね Not a bad bloke, really」とか「十分まともだね He’s decent enough」という言い方の方が信憑性があります。
アメリカのプラグマティズムには、知識は実用的で機能的、生産的なものであるという前提があるため、イギリス人のような曖昧さを嫌います。曖昧さは生産的でないからです。
プライバシーを重視し、個人的なことを必要以上に開示することを嫌うイギリス人に対して、アメリカ人は自己開示をします。なぜなら自己開示して情報を共有することは、生産的だからです。
アメリカ人は、他人に給与を尋ねることに抵抗がない人も多いですが、これはプライバシーを重視するイギリス人にとっては信じがたいことです。
~ ~ ~ ~ ~
テレビドラマにおけるイギリスとアメリカの違い
前回の記事で、企業の階層組織の特性を紹介するために「The Office(ジ・オフィス)」というテレビドラマを引用しました。ちょうどよい題材なので今回も引用しましょう。
2001年イギリスで初放送されてからブームとなったオフィスで働く人たちの日常を描いたコメディドラマで、その後アメリカ版が製作され、2005年から2013年までテレビ放映されました。私は当時アメリカにいて、アメリカ版を見ていましたが、このテレビドラマにおいても、両国の違いを見ることができます。
私が見ていたアメリカ版でさえ、独特な雰囲気がありますが、オリジナルのイギリス版は、日常生活の平凡さや仕事の無意味さ、さらに、皮肉、社会リアリズム、そして気まずさを前面に出したユーモアが支配しています。トーンは暗く、ぎこちなく、登場人物は控えめで、救いようがありません(笑)。
アメリカ版はぎこちなさは残るものの、心温まる物語で、そしてシニカルと言うよりは、もっと明るい楽観主義がバランスよく織り交ぜられています。登場人物も、より温かく、明るく、イギリス版のような哀れや不快感を覚えるような人物ではなく、もっと愛すべきキャラクターたちとして描かれていて、エピソードが進むにつれて、トーンはさらに明るく、彼らが恋をしたり、成長していく、アメリカ的なポジティブなストーリーに変わっていきます。
下のYoutubeはイギリス版とアメリカ版を比較したものです。またその次のYoutubeでは、イギリス版の上司であるデイビット・ブレントとアメリカ版の上司であるマイケル・スコットのやり取りが見られますが、その短いやり取りの中でさえも、両国の違いが分かって面白いです。
他にも「House of Cards(ハウス・オブ・カード)」や「Shameless(シェイムレス)」などイギリスのテレビドラマをアメリカ版にリメイクした番組はいくつかありますが、これらから両国の違いを比較するのも面白いかもしれませんね。
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
以上、イギリスの経験主義とアメリカの実用主義、それらがもたらす文化的違い、真実や知識の捉え方の違いについて説明しました。
両国は共に経験主義の伝統を共有していますが、イギリスの経験主義は懐疑主義と具体性に重きを置くのに対し、アメリカで発展した実用主義は、行動志向、問題解決志向です。
一般的に、イギリス人は慎重で、控えめで、暗黙のエチケットや個人のプライバシーを重視する一方、アメリカ人はより自信に満ち、オープンで、率直です。
イギリス人は慣習、そして実体験を好みます。これは経験主義的でボトムアップ的な思考と大まかに一致しています。対照的に、アメリカ人はトップダウン型の思考、そして明確さを好みます。
もちろん、この違いは一般論であって、すべての人に当てはまるわけではありません。
間接的な表現を好むアメリカ人もいますし、直接的な表現を好むイギリス人もいます。
さいごに、イギリス人とアメリカ人の考え方の違いを示す特徴的かつ分かりやすい7つの事例を列記して今回は失礼します。ここまで読んできて、これらの事例から、両者の違いの背景を何となく推測できるのではないでしょうか?
また、今回紹介したようなイギリス人の特性は日本人に近いと感じる人もいるでしょう。実際、イギリス人と日本人には多くの共通点があります。次回はイギリス人と日本人の共通点について書きます。
~ ~ ~ ~
イギリス人とアメリカ人の考え方の違いを示す7つの事例
1.列に並んでいる時の行動
イギリス人:静かに秩序をもって列をなし、雑談はせず、個人の空間とプライバシーを尊重する。
アメリカ人:列に並んでいる人と会話する。スペースを他人と共有していることをつながりのチャンスと捉える。
2.挨拶
イギリス人:「How are you?」と社交的に挨拶しているだけ。それ以上会話を続けたいわけではない。
アメリカ人:「How are you?」と声をかけることで、会話のきっかけにする。
3.雑談
イギリス人:天気など、差しさわりのない話題について話し、個人的な話はほとんどしない。
アメリカ人:早い段階から、個人的な質問をすることが多く、その方が友好的だと捉えられる。
4.感情の開示
イギリス人:感情を共有することは、段階的なプロセスであり、信頼構築のために長い時間をかける。
アメリカ人:早い段階から感情を共有し合い、信頼関係を築く。
5.意見の相違
イギリス人:あからさまに相手を否定することは失礼なので、「それは興味深いですね That’s interesting」と言いつつも、心の中では「クソだな Rubbish」と思っている。
アメリカ人:相手の意見に同意できない場合は「賛成しない I disagree」と正直に言う。
6.問題解決を探る時の行動
イギリス人:「これまで何がうまくいったのか?」を自問し、過去の枠組み、制度に基づき、慎重に物事を進める。
アメリカ人:「今何がうまくいくのか?」を自問したり、みんなでディスカッションする。過去に捉われず、自由に発想しイノベーションを生み出す。
7.計画が成功した時
イギリス人:「ラッキーだった」と控えめに表現し、自分の成功を誇張したり、自慢するのを避ける。
アメリカ人:自分の成功事例をアピールする。



