「所有から共有へ」「競争から協力へ」「個から繋がりへ」- リペアカフェ、地域支援型農業、トランジション・タウンなど、すでに世界中で実践されている市民主導の持続可能な脱成長(デグロース)の取り組みを紹介します。脱成長は、経済成長を最優先する社会を転換し、環境と人の幸せを重視して生産や消費を再設計しようとする考え方です。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
ジェイソン・ヒッケル(Jason Hickel)の著書『Less is More(邦題)資本主義の次に来る世界』が出版されてから5年が経ちました。本書への大きな反響もあって、今では、脱成長論(デグロース:Degrowth)は、気候変動や生態系危機をめぐる議論の主流に加わり、環境科学において確固たる地位を築きました。
一方で、脱成長の欠点についても多くの議論が交わされ、その可能性と課題についても議論されてきました。
ヒッケルは脱成長はいまだに誤解されていると言います。ただし、その誤解は次の3つのことを理解することで正すことができるとも言います。(1)
- 脱成長は発展途上国を対象としたものではなく、反開発でもない。富裕国、特にその国の中でも環境に対して圧倒的な責任を負う階層を対象としている。
- 脱成長はあらゆる生産を削ることではない。特に負のインパクトが大きく、かつ、必要とされていない生産を削減すること。
- 脱成長の目的は、生産を社会的・生態学的に有益な活動に向け直すこと。人の幸せを向上させ、社会を進歩させること。
これらは脱成長に関する文献をざっと読むだけで理解できるはずですが、脱成長を強く批判する人たちの多くは、実際は文献をよく読んでおらず、言葉から来る雰囲気だけで反論しています。
資本主義を取り入れている高所得国は、経済成長を持続させ、総生産量を永遠に増やすことを前提にして成り立っています。しかし、有限な世界の中で、それが持続可能ではないことは明らかです。
高所得国が短い期間で脱炭素化を達成するには、総エネルギー使用量を削減する必要があり、そのために不必要な生産を削減する必要があります。しかし、問題は、資本主義そのものが、資本家や大企業など、資産の大半を所有する上位数パーセントの人たちと、その活動を支援する政府によって支えられていることです。
彼らにとって生産の目的は、人の基本的ニーズを満たすことや環境目標を達成することではなく、経済を成長させ続けるために、必要なレベルを超えた生産と消費を実現し、利益を最大化して資本を積み増していくことです。
つまり、脱成長は、現代社会を支えるシステムや仕組みと相反する概念です。主流派の経済学は成長をデフォルトの目標として優先し、政治システムは成長を前提として設計され、経済成長がマイナスになることはネガティブに捉えられます。資本の蓄積と拡大から環境目標達成へとシフトしなければなりませんが、既存のシステム自体がそれを受け入れることに強く抵抗しているのです。
これを解決するために必要なことは、何よりもまず、達成したい目的を変えることです。システムを変えることは個人では到底できませんが、目的を変えることは一人ひとりが実践できます。
実は、世界中で多くの人たちがすでに自発的に共同体的な姿勢を取り入れ、生活をよりシンプルにしています。そのような人たちは、より多く消費したり、より多くの「物」を手に入れたりすることが幸せにつながるわけではないことを知っています。むしろ、多くの人たちは、人や自然とのより深い繋がりや適度なバランスを切望しているのです。
~ ~ ~ ~ ~
脱成長の実践
脱成長の議論には、政治、経済、文化、価値観、ライフスタイルなど、様々な要素が絡み合っています。そのため、様々な視点を持った人たちが様々な角度から関わっています。学者もいれば活動家もおり、それぞれ目標や考え方が異なります。
実際の生活や現場で資源利用を削減するための具体的なステップを実践する人もいれば、社会変革を実現するための政治的なアプローチを考える人もいます。脱成長をエコ社会主義と連携させるべきか、それとも草の根の水平運動を通じて広めるべきかといった議論もあります。
特に学術界においては、議論の多くがまだ探索的かつ概念的な段階にあり、過度に分析に傾倒し行き詰まる人もいます。一方で、脱成長を実践に移している人たちは、壮大な理論的議論ほど注目を集めないことがよくあります。すでに静かに進んでいますが、それはむしろ退屈で地味に見えるかもしれません。
今回は、そのような地に足のついた脱成長の実践例を紹介しましょう。これらの中には「脱成長」という言葉を使わずに脱成長を実現しているものも多くあります。
~ ~ ~ ~ ~
1.リペアカフェ(Repair Café)
リペアカフェは、過剰消費や使い捨て文化に反対し、壊れたら買い替えるのではなく、まだ使えるものは修理して長く使うことを推進する、2009年にオランダでマルティン・ポストマによって始まった運動です。核となる考え方はシンプルです。修理できるものは修理して使えばよく、新しいものに買い替える必要はありません。
カフェには修理に必要な道具や材料が揃っており、家電、家具、衣類、食器、おもちゃなど、壊れたものを持ち寄り、ボランティアと一緒に修理を行うことで、修理方法を学びます。
修理するものがなくても、コーヒーを楽しんだり、他の人の修理を手伝ったりすることもできます。読書テーブルで修理やDIYに関する本をめくって、インスピレーションを得ることもできます。
現在、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアなど、数十カ国に約4,000のリペアカフェが存在します。そのほとんどはボランティアによって運営され、自治体、図書館、NGOなどの支援を受けています。
日本の「もったいない」という言葉がオックスフォード英語辞典に「mottainai」として収録されるなど、モノを大切にする日本の伝統的な価値観が世界的に広がっています。しかし、日本では、京都で京都リペアカフェが運営している以外は、リペアカフェの継続的な取り組みは確認できません。
「モノを大事にする」価値観はまだ残っているものの、日本では「地域の人たちと何かを一緒に取り組むこととそれを継続すること」が様々な要因から難しく、そのような活動に参加できるような仕組みを少しづつ取り戻していく必要があるのかもしれません。
~ ~ ~ ~ ~
2.コモニング(Commoning)
コモニングとは、行政やトップダウンによる管理ではなく、住民たちが協力し、公平性、相互責任に基づいて、資源を共有し、管理し、大切に守っていくことです。土地、森林、水といった資源そのものだけでなく、知識や経験といった資源、関係性やルール、責任の共有も含まれます。
コミュニティガーデンは、コモニングの一例です。共有スペースに何を植えるか、どう管理して、収穫物をどう分配するかを共に決めます。
共有工具ライブラリー、コミュニティフリッジ(共有冷蔵庫)など、隣人たちが、ある道具や設備を共有し、その利用方法、管理方法について話し合ってルールを決めて運用することもコモニングです。先ほど紹介したリペアカフェもこの枠組みに含まれます。
つまり、コモニングは、共有資源に関して共同の意思決定をおこない、責任を持って共同で管理運用していく広義な概念です。
日本のいわゆる「草の根運動」をイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、どちらも、市民主導、自発的参加、コミュニティ重視という点では共通していますが、「草の根運動」が、政策への反対運動や、特定の政治的、社会的な「働きかけ」の性質が強い一方で、コモンズは、「共有資源を共同で管理する仕組みをつくって、それを継続すること」が目的で、運動というよりは、実践や関係性という意味合いが強いです。
以前紹介した「アセット・ベースド・コミュニティ・デベロップメント(ABCD)」は、コモニングよりも地域福祉や地域再生という意味合いが強いですが、「ないものに焦点を当てるのではなく、すでにある資産に目を向ける」という点で強く重なる取り組みモデルです。
~ ~ ~ ~ ~
3.農業コミュニティ(コミュニティ支援型農業)
農業コミュニティ(コミュニティ支援型農業、Community-Supported Agriculture:CSA)は、生産者(農家)と消費者が直接契約を結び、収穫を共有するモデルです。「農場を維持する仲間」という位置づけで、野菜や果物を買うだけでなく、農場を共同で支えます。
消費者は作物の代金を季節前に前払いし、生産者は計画に沿って農業経営を行います。生産者と消費者の共同体的な関係のもと、生産リスク(豊作・不作)も消費者と共有します。
単なる野菜購入とは違い、「農業体験」「援農参加」「農家との交流」などが含まれる場合があり、消費者側の積極的な関与が特徴です。これは市場に基づいた食料供給とは異なる食の再構築を目指す脱成長的な仕組みです
1986年に設立されたアメリカ・ニューハンプシャー州にある共同農場「テンプル=ウィルトン・コミュニティ・ファーム(Temple-Wilton Community Farm)」は、世界でも最も初期のコミュニティ支援型農業(CSA)モデルの1つとして知られています。農場の年間必要経費を公開し、会員がその費用を分担、運営について議論するなど、共同経営色がかなり色濃いCSAです。
イリノイ州で1990年から農産物の栽培を開始しCSAとして長年続いてきた歴史ある「アンジェリック・オーガニックス(Angelic Organics)」も、CSAモデルとして人気の高かった例で、会員(消費者)は出資者(shareholder)として参加し、季節の収穫物を受け取る仕組みでした。残念ながら、2024年に創立者の健康事情で閉鎖されましたが、後継者が見つからず、苦渋の決断で閉鎖したことがホームページに残されたメッセージから読み取れます。
ニュージャージー州の「ラトガーズ学生サステナブル農場(Student Sustainable Farm at Rutgers)」は、ラトガース大学の学生農場で、地域住民150軒ほどが年間シェアの契約を結び、季節の野菜を受け取っています。教育・学習と連動したCSAの好例です。
ニューヨーク州の「ソウル・ファイア・ファーム(Soul Fire Farm)」のように、食の正義と人種的不平等をかけ合わせて、共感する消費者から支援を募るCSA農場もあります。低所得家庭向けのプログラムなど、社会課題と結びついたユニークなCSAの実践例として注目されます。
アメリカでは、「ロクスベリー・ファーム(Roxbury Farm CSA)」のように、1,000世帯以上が参加する大規模CSAがある一方で、日本ではCSAの普及は欧米ほど進んでいません。
日本では、CSA(地域支援型農業)あるいは類似の取り組み事例として、例えば、神奈川県大和市の「なないろ畑」は、消費者が前払いで野菜を購入したり、会費を払ってサポートする消費者との関係性があります。
また、北海道長沼町の「メノビレッジ長沼」や、つくば市の「飯野農園」など、日本各地で少数ながらCSA実践例が報告されています。
農業関連の情報発信メディアであるミノラスで、その他の国内のCSAの取り組みや課題を紹介しています。農研機構のホームページからは「CSA(地域支援型農業)導入の手引き」がダウンロードできます。
日本では、行政や自治体が土地を小さく区分して一般市民に貸し出すいわゆる「市民農園」は定着していますが、個人や家族の趣味として野菜栽培体験をするスペースに過ぎず、通常、農家との接点はありません。
先ほども述べましたが、日本では、地域共同体の希薄化が進み、知らない人との深い関係を避ける傾向や、地域で役割や責任を負うことへの負担感、社会運動色が強いものに参加することへの抵抗感があります。また、例え参加したくても、仕事や子育てに忙しく、そのような時間的余裕がありません。
日本ではCSAのような消費者が生産者と直接繋がることに対する社会的、文化的障壁が高いのかもしれません。欧州型のCSA(例えば欧州最初期のCSAであるドイツの「Buschberghof」)では、会員総会、予算議論、労働参加が一般的ですが、そのような参加への心理的、構造的な障壁を下げるような社会の変化がなければ、このような取り組みの拡大は難しいでしょう。
また、日本の消費者は「一定の価格を払えば、一定品質以上の商品が手に入る」という期待感がとても強く、生産者と消費者の線引きが明確です。CSAの「価格は農場維持費の分担であり、収量や品質は保証されない」という仕組みは受け入れがたいかもしれません。必要以上に多く野菜をもらっても困る家庭も多いでしょう。むしろ、日本では、より受け入れやすいと思われる「地産地消」「食の安全(有機農法)」「支え合い」などの視点からアプローチするのが良いのかもしれません。
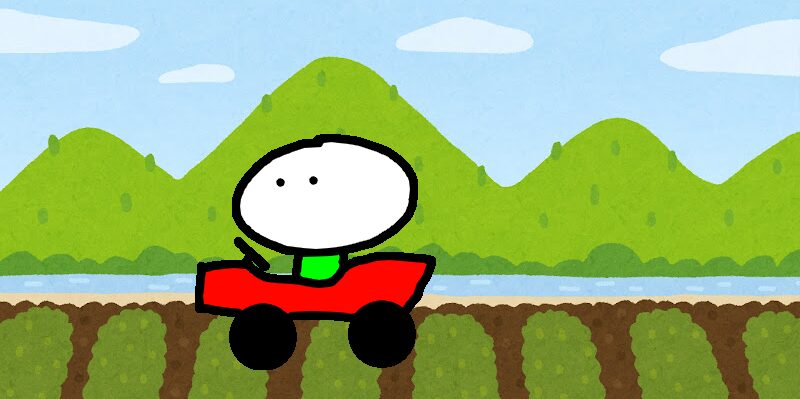
~ ~ ~ ~ ~
4.トランジション・タウン(Transition Towns)
トランジション・タウンは、気候変動と化石燃料依存からの脱却を目指す草の根運動です。2005年にイギリスのトットネスで、環境活動家であり作家のロブ・ホプキンス(Rob Hopkins, 1968 – )によって始まり、現在では世界50カ国以上、数千のコミュニティに広がっています。
トランジション・タウンの核となる考え方は、「持続可能で回復力のある地域コミュニティを、住民自身の手で創り出す」ことです。中央政府や大企業の変化を待つのではなく、地域レベルで「今できること」を始めることを重視します。
例えば、次のような取り組みです。
- 地域の食料自給率向上:コミュニティガーデン、都市農業、地産地消の推進など、地域で食べ物を育て、流通させる仕組みを作る。
- 再生可能エネルギーへの移行:地域で太陽光発電、風力発電プロジェクトを立ち上げ、エネルギーの地産地消を目指す。
- 地域通貨の導入:地域内での経済循環を促進するため、独自の地域通貨を発行し、地域経済の自立性を高める。
- スキルシェアとワークショップ:修理、保存食作りなど、持続可能な暮らしに必要なスキルを地域内で共有する。
- 心理的・社会的側面:気候変動への不安や孤立感に対処し、コミュニティの絆を強める。
海外の具体的な事例として、トランジション・タウン発祥の地であるイギリスのトットネス(Totnes)は、地域通貨「トットネス・ポンド」の導入、コミュニティ農園、再生可能エネルギープロジェクトなど、包括的な取り組みで知られています。2010年代には地域のエネルギー会社を設立し、住民が株主となって太陽光発電に投資する仕組みも作りました。
イギリスのブリストル(Bristol)は、ヨーロッパ最大のトランジション・タウンの1つで、地域通貨「ブリストル・ポンド」は一時、市長の給与もこの通貨で支払われるなど、行政との連携も進みました。
その他様々な事例が、Transition Network Internationalのホームページなどで紹介されています。日本でも2008年からトランジション・タウンの運動が始まっており、その活動はトランジション・ジャパンのホームぺジで確認することができます。
トランジション・タウンは、「脱成長」という言葉を前面に出してはいませんが、その実践は脱成長の理念と深く結びついています。グローバルな経済成長や大量生産・大量消費に依存するのではなく、地域の自立性を高め、地域内での循環経済を目指すという点で、脱成長的なアプローチと言えます。
また、トランジション・タウンは、単に「消費を減らす」という否定的なメッセージではなく、「より良い暮らし方を創造する」というポジティブなビジョンを示している点が特徴です。これは、脱成長が目指す「人の幸せ」と「環境負荷の低減」の両立という理念とも一致しています。
なお、トランジション・タウンの創設者ロブ・ホプキンスによって2008年に書かれた『トランジション・ハンドブック』の無料版は(英語版ですが)、このリンクからダウンロードできます。
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
今回は市民主導型の脱成長の取り組みについて紹介しました。
リペアカフェ、コモニング、コミュニティ支援型農業、トランジション・タウンなど、これらの実践は、いずれも「成長のための成長」ではなく、「人の幸せと環境の持続可能性」を中心に据えた活動です。
これらの多くは「脱成長」という言葉自体を掲げてはいませんが、実質的に脱成長的な価値観を体現しています。つまり、理論や政治的イデオロギーを前面に出すのではなく、日常生活の中で脱成長を実践しています。
また、これらの取り組みに共通するのは、「所有から共有へ」「競争から協力へ」「個から繋がりへ」という価値観の転換です。リペアカフェでは修理技術とツールを共有し、コモニングでは資源と責任を共有し、CSAでは収穫とリスクを共有し、トランジション・タウンでは地域の未来を共に創造します。これらは、資本主義的な個人主義や消費主義とは異なる生き方と社会のあり方を示しています。
このようなボトムアップの取り組みは、個人でも始められ、すぐに効果を実感できるのが強みです。特別な資格や資金がなくても、地域のリペアカフェに参加したり、コミュニティガーデンで野菜を育てたり、地域通貨を使ってみたりすることで、誰もが脱成長的な実践に関わることができます。
一方で、市民の自発的な活動だけでは、システム全体を変えることは困難です。いくら個人が努力しても、化石燃料に依存したインフラ、大量生産・大量消費を前提とした経済システム、成長至上主義の政治が変わらなければ、真の意味での脱成長社会への移行は実現しません。
次回は、行政主導型、つまり、世界各国の自治体や政府による脱成長の取り組み事例を紹介します。政策レベルでどのような実験が行われているのか、そして市民の実践と政策がどう連携できるのかを探ります。ボトムアップとトップダウンの両輪が揃ってこそ、脱成長社会への移行が現実のものとなるでしょう。
~ ~ ~ ~ ~
参考文献
(1) “Interview with Jason Hickel: Degrowth is a gateway into socialist thought for the 21st century“, The BREAK—DOWN, 2025/8/6.





